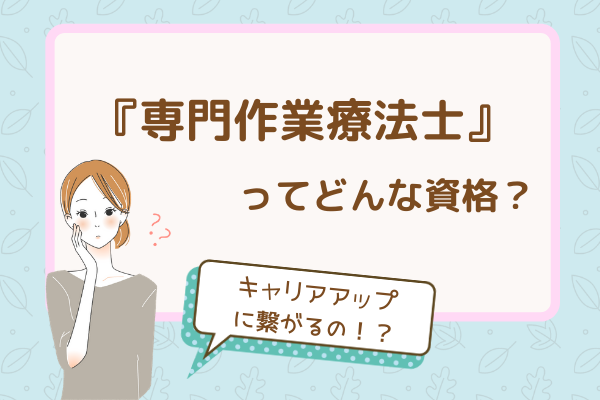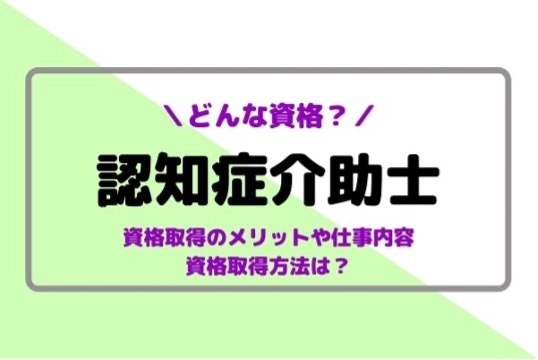作業療法士の将来性はない?現状と今後から考えるべきこと
作業療法士人口の増加に伴い「将来が不安」と感じる方が増えている今、作業療法士の現状と今後から作業療法士の将来性について考えてみませんか?
更新日:2023年04月06日
公開日:2021年09月07日
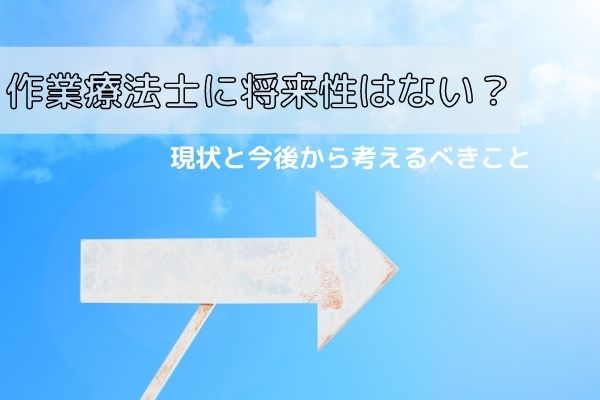
作業療法士として活躍している方は年々増えている傾向にあり、国家資格のなかでも人気の高い資格のひとつとなっています。
その一方で、資格取得者が増えている状況から、現在作業療法士として活躍している方のなかには「将来が不安」「作業療法士は将来性がない職種なのでは?」と考える方も多いかもしれません。
そこで、本コラムでは作業療法士の現状と今後考えられることを比較しながら、『作業療法士の将来性』について考察していきます。
また、作業療法士の将来性について考えるにあたり、作業療法士が『将来も活躍するために必要なこと、身につけておくべきこと』についてもご紹介していきますので、将来に不安がある方はぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
目次
作業療法士の将来が不安!現状はどうなっている?
高齢者の増加に伴い需要が増えているといわれる作業療法士。実際に作業療法士を志す人は年々増えていますが、資格取得者数や活躍の場所、そして求人状況はどのようになっているのでしょうか。
将来性について考えるにあたり、まずは作業療法士の現状について確認していきましょう。
全国の作業療法士数の推移
一般社団法人日本作業療法士協会による2019年度日本作業療法士協会会員統計資料によると、2020年3月時点における作業療法士の有資格者数は94,255人です。そのうち、協会に登録している会員(62,294人)の男女の内訳は男性が23,919人、女性が38,375人となっており、男女比率では男性が約38.4%、女性が約61.6%の割合で分布しています。
作業療法士資格取得者の推移のデータをみると、作業療法士の資格取得を志す人は年々増えている傾向にあることが分かり、年間でみると約4,700人もの人が作業療法士の国家資格を取得している状況となっています。
これは、国による養成校の規制緩和により専門学校などが増加したことが理由のひとつとして挙げられますが、就職先の選択肢が広がったことにより作業療法士を志す人が増えていると推察できます。
とはいえ、現状としては令和3年度における理学療法士の資格取得者数192,327名と比較するとまだまだ作業療法士人口は少なく、リハビリ職のなかで飽和している状況とはいえないでしょう。
しかしながら、今後さらにハイペースで作業療法士の資格取得者が増えていくと、就職に影響を及ぼす可能性は少なからず出てくる可能性はあるかもしれません。
★こちらのコラムもおすすめ!
【2020年最新】作業療法士国家試験の合格率と推移について
作業療法士の活躍場所
現状、作業療法士が活躍している場所は病院のリハビリテーション科といった医療機関をはじめ、介護・福祉施設や行政・地域が担う地域包括ケアセンターなど、また特別支援学校といった教育機関などが挙げられます。作業療法士が活躍している領域は、「身体障がい領域」「老年期障がい領域」「精神障がい領域」「発達障がい領域」の4つに分類されますが、そのなかでも最も多くの作業療法士が活躍している領域が病院における「身体障がい領域」です。
「身体障がい領域」では、怪我や病気などの後遺症による身体機能の回復を目的としたリハビリを中心とし、日常生活に必要な細かい動作のリハビリが実施されています。
また、高齢者人口の増加により訪問リハビリでの需要も高まっています。
作業療法士の求人状況
作業療法士の求人は、地域や施設によってバラつきはあるものの、活躍の場が多く需要も高い職種であることから安定して募集がある状況です。リハビリ職の転職エージェントであるPTOTSTワーカーでは、令和3年8月末時点における全国の作業療法士求人が1万4千件以上あり、常時新たな求人も次々と掲載されています。
とはいえ、施設によっては需給状況が異なっているのが実情で、一部の病院では必要な人員が充足していたり、採用倍率が他の施設より高かったりするところもみられます。
一方で、介護施設や福祉施設では作業療法士不足により急募となっているところもあるなど、働く領域によって求人数には偏りが出ていることもあります。
現時点では作業療法士の就業先は多くありますが、年々活躍の場が増えていることで作業療法士人口も増加しているため、今後の就職活動においては競争率が高まっていく可能性はあるでしょう。
作業療法士の将来性は今後どうなる?
資格取得者が増えていることで確実に作業療法士人口は増加の一途をたどっていますが、現状としては活躍の場も多く求人状況も安定しています。しかし、今後さらに作業療法士が増加し続けていくことで、「将来的に需要がなくなり就職先などが限定されていくのでは?」と不安を感じる方も少なからずいるのではないでしょうか。
作業療法士の将来性を考えるうえでは、現状をふまえて先を見据えた行動がキャリア形成を作るうえで重要なカギとなりますが、作業療法士は今後どのような変化を迎えていくのかでしょうか。
日本が抱える課題や技術の発展などから、作業療法士の将来を考えてみましょう。
高齢化により需要は増加
2025年には「3人に1人が75歳以上の高齢者」となる日本では、超高齢化社会を迎える日もそう遠くないものになってきました。現在でも、病院だけでなく介護施設や福祉施設を利用する高齢者は増えていますが、今後はさらに利用者が増加することが予想されます。
そうなると、確実に作業療法士を必要とする施設は増え、高齢化によるリハビリの需要はますます高くなっていきます。
また、超高齢化社会を迎えるにあたり認知症患者も増加の一途をたどっていますが、75歳以上の高齢者が増えることでさらに認知症に対する作業療法の必要性も高まっていくことが考えられます。
認知症に対する知識や経験はもちろんのこと、認知症予防に対する働きかけも作業療法士が担う重要な役割になってくることでしょう。
地域による包括的なケアが重要視されている今、作業療法士に求められる今後の課題としては、高齢者に向けて認知症予防としてできることを啓発する活動などの拡大などが挙げられます。
活躍の場所はさらに広がりをみせる
前述した通り、超高齢化社会を迎える日本ではリハビリの必要性はますます高くなっています。そのため、作業療法士の活躍の場はさらなる広がりをみせることとなり、認知症専門病院などや介護施設、福祉施設や行政・地域が担う地域包括センターなどにおいても、今まで以上に活躍が期待されていくと考えられます。
また、高齢者だけでなく精神疾患や発達障がいなどを抱える患者の増加によっても、作業療法士の活躍の場は広がりをみせていくことも予想されます。
少し前までは、精神疾患や障がいに対する考え方はその人の性格からくるものであったり、個性として受け入れられたりすることが多くありましたが、医学の進歩やメディアなどによる情報発信により、病気や障がいであると認められて治療を行うケースが増えてきました。
すぐに完治する病気とは異なり、精神疾患や発達障がいなどの治療には時間を要する場合が多いですが、身体のリハビリだけでなく日常に対する「生きづらさ」を感じている方の心の拠り所となるケアにも長けている作業療法士は、ますます今後必要とされていくでしょう。
AI技術の発展が考えられる
近年、ニュースなどでも見かけることが多くなったAI(人工知能)技術は、日々進歩を続ける科学技術によって人々の暮らしを豊かにするといわれています。AI技術の発展によりあらゆる職場でその活躍が期待されていますが、医療分野においても10年後あるいは20年後には当たり前に導入されているかもしれないと考えられています。
作業療法士の仕事に関わるリハビリの分野では、蓄積されたリハビリのデータをもとに適切で効果的なリハビリプログラムを作成したり、リハビリの結果をもとに効果を検証したりすることがAI技術によって可能になるといわれています。
また、AIは365日24時間稼働することが可能なため、リハビリ以外の業務に費やす時間の削減といった「人件費の削減」にも大きく貢献するだろうともいわれています。
しかし、作業療法士の主な仕事であるリハビリ業務は専門知識や技術を用いて人の手によって行われるものであり、AI技術が直接患者のケアを行うことはもちろんできません。
そのため、科学の進歩によってリハビリ以外の業務が効率的に行えるようになったり働き方が変わったりしたとしても、作業療法士の存在は必要不可欠であり、今後もあらゆる領域において活躍は続いていくといえるでしょう。
作業療法士が将来も活躍するために必要なこととは
高齢化といった問題や精神疾患などの認知によって作業療法士の需要はますます高くなっていくことが予想されますが、一方で資格取得を目指す人が今後さらに急増していくと、就職先が限定されたりキャリアアップが難しくなったりする可能性があります。そのため、多くの作業療法士が活躍しているなかで自身の将来性を考えるにあたっては、今後目指していきたい方向性を固め、それを実現するための行動を起こすことが大切になってきます。
では、将来を見据えて作業療法士としてさらなる活躍を目指すには、どのようなことが必要となってくるのでしょうか。
専門性をより高めるための資格や知識
自身の将来性を考えたときに、これからの作業療法士に必要なことはほかの作業療法士と差別化を図りながら自身の価値を高めることです。そのためには、作業療法士としての専門性をより高めることが大切で、特に自身が進みたい分野、極めたい分野における専門知識を深めることが重要です。
特に、作業療法士の専門性を高めるうえでは、作業療法士の活躍領域で活かせる専門資格を取得することが明確な知識習得の結果として分かりやすいでしょう。
専門資格の取得は転職やキャリアアップにも活かすことができるので、非常におすすめです。
数多くいる作業療法士のなかで、仕事に活かせる+αの資格を取得していることは自身のアピールポイントとなるだけでなく、各分野におけるチーム医療などでも活躍の場を広げることにつながるはずです。
作業療法士が取得できる資格はいろいろですが、作業療法士として目指したい専門領域が決まっている場合、以下のような資格の取得を目指してみるのもよいでしょう。
<作業療法士の専門性を高める+α資格>
・専門作業療法士
・認定作業療法士
・呼吸療法認定士
・認知症ケア専門士
・心臓リハビリテーション指導士
・糖尿病指導士
・栄養サポートチーム(NST)専門療法士
★こちらの記事もおすすめ!
作業療法士のスキルアップ|何から始める?レベル別に解説!
進む医学に対し日々研鑽を積む姿勢
高齢化社会の進展と医療技術の進歩によりリハビリ分野での作業療法士の需要は高まっている一方で、今後も作業療法士が増え続けると需要よりも作業療法士の数が上回り、作業療法士のなかで『できる人・できない人』の選別が進められる可能性があります。そういった可能性があるなかで将来も作業療法士として活躍しつづけるためには、職場で求められる人材になることが大切です。
職場で求められる人材として『できる人』と認定されるには、進む医学に対し日々研鑽を積む姿勢が改めて大切になってきます。
作業療法士として自己研鑽を続けるうえでは、
・リハビリテーション医療の最新の動向をこまめにチェックする
・作業療法に関連する研修会や講習会、セミナーなどに参加する
・学会発表をする、参加する
・海外の論文を読む
・自ら論文を投稿する
・専門資格を取得する
作業療法士は国家資格があれば働くことが可能なため、なかには一定の知識量でそれ以上の勉強をせず流れ作業のように仕事をこなそうとする人もいるかもしれませんが、積極的に学ぶ意欲と姿勢をもって作業療法と向き合うことは、自身のスキルアップ、将来のキャリア形成に大きく結びつくでしょう。
身につけた知識やスキルを共有、発信しようとする行動力
作業療法士として日々学び続ける姿勢は仕事への向上心を高め、将来求められる人材へと近づくための行動としてプラスに働きますが、自己アピールという面では自己発信力があるとなおよいでしょう。自己発信力のある人は、学会や研修会などに積極的に参加するだけでなく、そこで得た知識やスキルを職場で共有する、または外部へ発信するといった行動力があり、作業療法に関わるチーム全体の知識の底上げに貢献しようとする姿が高く評価されます。
作業療法士として自己研鑽を積むうえで知識をたくさん吸収することはもちろんよいですが、ときにはアプトプットを行い経験や学びを日々の業務や発言に反映させるということも必要です。
そこに前述したような行動力が伴えば、周囲からの認知度は上がることはもちろん、人に教える技術が身についたり人脈が広がったりといった複数のメリットがうまれます。
動画配信やビデオ通話などが当たり前になっているなか、将来的には遠隔で患者さんとコミュニケーションをとる方法を導入する施設も増えてくる可能性もあります。
経験や知識を普段から人に共有したり発信したりしている人は、このような時代がやってきても人に伝える力が備わっていることから、いろいろな場面で重宝されるはずでしょう。
AI技術には真似できない対人スキル
医療費削減や人材不足の解消といったマイナス面をカバーするために、将来的にリハビリテーション医療においてAI技術に頼る可能性がでています。そういった将来を見据えたときに、作業療法士としてこの先も生き残るためにはAI技術には真似できない『人間味のある温かなコミュニケーション力』を身につけておくことも大切です。
作業療法士は患者さん一人ひとりの日常生活や社会生活の再建に大きく関わっていくため、心身の状態に合わせた言葉かけなど、対人だからこそできる温もりのあるケアやコミュニケーションが求められます。
いくらAI技術が発展したとしても、相手の立場に立ち都度変化する患者さんの心情に寄り添ったケアは人にしかできない部分であり、日常生活に必要な作業を通してリハビリを行うことは作業療法士にしかできません。
そのため、「この人となら頑張ってリハビリを続けていきたい」と思ってもらえるような作業療法士は、今後も患者さんから必要とされていくでしょう。
現在の職場に将来性が見出せない場合は転職も視野に
自身の作業療法士としての将来性を考えたときに、現在の職場でキャリア形成が難しいと感じた場合は転職を視野に入れてみるのもひとつの手です。作業療法士が活躍できる場所は現状でもかなり豊富にあり、どのような科目で働くか、あるいはどのような施設で働くかによって実施するリハビリの内容は大きく異なります。
そのため、自信の今後を考えるにあたっては、将来なりたい姿に近づける環境で働くことも重要なことといえます。
そのうえで、これからの転職に求めるポイントにおいては、
・スキルアップするための学びの機会が多くあるか?
・各分野のプロフェッショナルとして働ける環境が整備されているか?
将来なりたい姿に向かって前向きな転職を行ううえでは、スキルアップしたいという自身の気持ちだけでなく周囲がスキルアップを後押ししてくれる環境であることも大事になってきます。
スキルアップできる環境が整っている職場かどうか見極める際は、
「定期的に勉強会や講習会を開いているか?」
「積極的にセミナーや研修、学会などへの参加を進めているか?」
といった学術的な取り組みの実施内容に着目してみるとよいかもしれません。
また、特定の分野で活躍したいと考えている場合は、
「専門分野に特化したリハビリを実施しているか?」
「特定の疾患に対し作業療法士の介入が実施されているか?」
などといった点に着目してみるとよいでしょう。
栄養サポートや摂食嚥下支援、認知症ケア、排尿ケアといったそれぞれのチーム医療にどれだけ作業療法士が介入しているかどうかを調べることで、その職場における作業療法士の役割も理解できるはずです。
転職の相談はPTOTSTワーカーへ!
PTOTSTワーカーは、作業療法士をはじめリハビリ職として働く方の転職を完全無料でサポートしております!長年各医療機関と人材紹介で培った信頼性から、業界内でもトップクラスを誇る求人数をはじめ、各職種を専門とする経験豊富な転職のプロによる転職支援を行っております。
「転職で給与アップを目指したい」
「無理のない通勤距離で働ける職場を探したい」
「ライフワークバランスを重視した働き方を実現したい」
「人間関係に悩まない職場で働きたい」
「特定の分野で活躍したい」
「新しい分野にいレンジしてみたい」
など、転職にお悩みがある方はぜひ一度PTOTSTワーカーまでご相談ください!
■ PTOTSTワーカーではWeb面談・Web面接を実施中!
■PTOTSTワーカーがはじめての方へ
■PTOTSTワーカーでお仕事を探す
★こちらの記事もおすすめ!
作業療法士(OT)の転職!転職の失敗例から学ぶ転職を成功させる5つのポイント!
最新コラム記事
-

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
-

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
-

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
-

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
-

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
-

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説
理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説