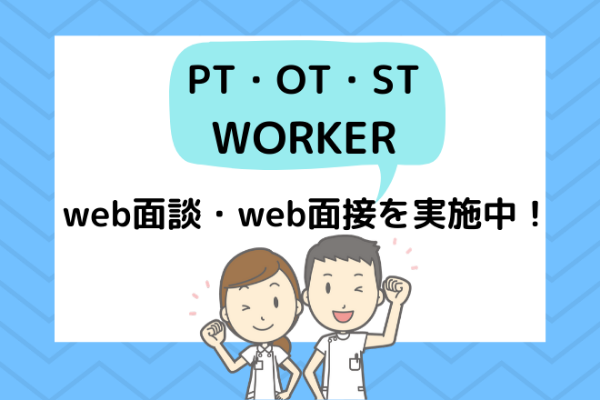理学療法士には資格が必要?取得までの手順やおもな勤務先をご紹介
理学療法士には資格が必要?取得までの手順やおもな勤務先をご紹介
更新日:2023年01月16日
公開日:2023年01月05日

少子高齢化社会の影響で医療の需要が高まっている今、理学療法士を目指す人は年々増加しています。しかし理学療法士に必要な知識や資格をあまり把握していない人も多いです。この記事では理学療法士を目指している人のために、資格の有無についてご紹介します。
目次
理学療法士に必要な資格とは?
まずは理学療法士とはどのような仕事を行う職業なのか、資格が必要なのかをここで説明します。
理学療法士とは?
理学療法士はケガや病気が原因で障害を負った人に対して、元の生活を送れるようにリハビリテーションを提供することがおもな仕事です。リハビリは筋トレ・ストレッチなどの運動や機械による治療、日常動作の指導といったように、その内容はさまざまです。患者さん全員に同じリハビリを提供するのではなく、その人の障害の程度にあわせて適切な治療計画を作成します。
理学療法士の他にも「作業療法士」と「言語聴覚士」という種類の職業もあります。それぞれ職業は提供する内容は異なりますが、どれも共通していえることは、患者さんの支援につなげるためのリハビリを行うことです。
理学療法士になるには国家資格が必要
理学療法士として仕事をするためには国家資格が必要です。国家資格を取得するには養成校に3年以上在籍して知識と技術を身につけた後、国家試験に受験して合格しなければいけません。そのため理学療法士は、資格がない状態でいきなりはたらくことができません。
理学療法士の資格を取得するまでの流れ
理学療法士として仕事をするためには、資格が必要であることがわかりました。ここでは実際に資格を取得するまでの流れについて説明します。
学校に入学する
まずは専門学校・大学に入学して、理学療法士に必要な知識と技術を学びます。専門学校は理学療法士に特化したカリキュラムが組まれるので、その道一本で考えている人におすすめです。専門学校には3年制と4年制の学校に別れており、早く理学療法士として就職したい人は3年制が向いています。しかし4年制と比べると授業の量とスピードが早いので注意が必要です。
大学は専門学校と異なり、さまざまな分野を学べるため、途中で理学療法士以外の道も選択できます。学生も全員が理学療法士を目指しているわけではなく、別の分野の学生と交流しやすいのも1つの特徴です。学費がいくらかかるのかは学校にもよりますが、以下を目安にしておくといいでしょう。
・私立大学:600万円前後
・国立大学:250万円前後
・3年制の専門学校:400万円前後
・4年制の専門学校:500万円前後
また通信制では理学療法士の資格は獲得できないので、必ず専門学校・大学に入学する必要があります。
国家試験に合格する
国家試験を受験して、合格すれば資格の取得が可能です。国家試験の内容は「一般問題」と「実地問題」の2種類に分かれており、どちらもマークシート式の問題です。一般問題は160問あり、1問1点。実地問題は40問あり1問3点で計算されます。厚生労働省によると、2022年の国家試験では、総得点は164点以上、実地問題は40点以上が合格ラインでした。
また日本理学療法士協会によると、2022年度の国家試験の受験者数は12,685人で合格者は10,096人、合格率は79.6%といわれています。
出典:第57回理学療法士国家試験及び第57回作業療法士国家試験の合格発表について – 厚生労働省
統計情報|協会の取り組み
理学療法士免許の申請を行う
国家試験に合格したら、理学療法士の免許の申請を行います。各保健所に申請書や診断書、登録済証明書用はがきなどを提出すると、申請して約2〜3か月後に理学療法士免許が届きます。申請中はすでに就職しているケースがほとんどなので、免許が届いたらすぐに勤務先の上司に報告しましょう。
資格取得後の理学療法士の勤務先
理学療法士の資格を取得すれば晴れて仕事を行えますが、実際にどのような勤務先があるのでしょうか。ここではおもな勤務先についてご紹介します。
医療施設
医療施設は理学療法士の勤務先のなかでも一番割合が多いとされています。医療施設も種類によってさまざまあり、おもに以下のような病院があります。
・急性期病院
・回復期病院
・療養型病院
など
これらは患者さんが入院する時期がそれぞれ異なるため、リハビリを行う期間や注意すべきポイントが変わります。その他にも精神科病院や小児病院などもあり、仕事内容もその病院にあわせて大きく変化します。そのためリハビリを行いたい時期や興味がある疾患について考えたうえで、希望の医療施設に就職することが大切です。
福祉施設
福祉施設は医療施設の次に割合が多い勤務先です。福祉施設には以下のような種類があります。
・介護老人保健施設
・デイサービス
・特別養護老人ホーム
など
福祉施設の利用者さんは比較的症状が落ち着いており、在宅で過ごされている人も多いです。そのため福祉施設では今後も安全に家で暮らすために、身体機能を維持することがおもなリハビリの目的です。
また障害者や障害児を対象としている福祉施設で仕事をする理学療法士もいます。その場合既存の機能の改善ではなく、新しい機能の獲得を目的にリハビリを実施します。
訪問看護ステーション
訪問看護ステーションでは、利用者さんの自宅に訪問してリハビリを提供します。他の施設と異なり、利用者さんが実際に住んでいる環境でリハビリを行うのが大きな特徴です。年単位にわたってリハビリを利用する人もいるため、長期間利用者さんの暮らしに寄り添いたい人におすすめです。
訪問リハビリは基本的に1人での行動なので、状況を的確に判断しつつ、なにかあったときの素早い連絡が求められます。そのため、理学療法士としてある程度経験を積んだ後に就職するケースが多いです。
教育・研究施設
臨床現場ではなく教員として養成校ではたらき、学生に教育を行う道もあります。教員には5年以上の理学療法士としての経験が求められるため、すぐに養成校で仕事ができるわけではありません。理学療法士として経験を積んだ後の選択肢として考えておいた方がいいでしょう。
また専門施設や大学院で、研究を中心に行う理学療法士もいます。これらの勤務先は間接的ではありますが、未来の医療業界をよりよくするための仕事といえるでしょう。
スポーツ分野
フィットネスクラブやプロのスポーツクラブなどで仕事をする理学療法士もいます。この分野のリハビリ対象はプロスポーツ選手や10〜20代の若い人などで、ケガを予防しつつ運動能力を高めるためのトレーニングを行います。
他の施設と比べるとリハビリを対象とする年齢や身体機能がまったく異なるため、医療現場とはちがった雰囲気で仕事を行えるでしょう。もともとトレーナーを目指して理学療法士になる人もいるので、スポーツ分野に興味がある人は1つの選択肢として考えてみましょう。
理学療法士の仕事内容
さまざまな勤務先についてご紹介しましたが、実際にどのようなことを行うのでしょうか。ここでは理学療法士の具体的な仕事内容について説明します。
リハビリ前の評価
患者さんや利用者さんにリハビリを実施する前に評価を行い、具体的な治療プログラムを立てます。その人に適切なリハビリを提供するためには、評価を正確に行わなければいけません。そのため評価は理学療法士のなかでも重要な仕事の1つといえるでしょう。その人の疾患や既往歴、生活歴などの基本的な情報はもちろん、以下のような細かい項目も評価します。
・筋力
・関節可動域
・持久力
・バランス
・血圧
など
これらの評価は定期的に行うことで、患者さんの身体の経過を追う指標にもなります。評価を繰り返し行い、そのときの状態にあわせたリハビリプログラムを適宜変えていきます
運動療法
運動療法は患者さんに運動を促すことで、筋力や関節可動域、バランス機能の改善を目指す治療方法です。運動療法にはおもに以下のような内容があげられます。
・筋力トレーニング
・関節可動域訓練
・筋持久力訓練
・バランス訓練
・日常生活動作訓練
このように、さまざまな運動療法で身体機能を改善させ、最終的に日常生活に必要な動作の獲得を図ります。運動療法は患者さんの動きの改善に直結しやすい内容でもあるため、実際のリハビリ場面で行われる頻度は非常に多いです。
物理療法
物理療法は温熱や電気などの物理エネルギーを利用した機器を使用し、痛みの緩和や血行の促進を促す治療方法です。代表的な物理療法には以下があげられます。
・温熱療法
・寒冷療法
・電気療法
・水治療法
上記の治療はそれぞれ目的や効果が異なります。たとえば温熱療法では熱の力で患部の血流の循環を促し、リラクゼーション効果を生む一方、寒冷療法では患部を冷やして血流を低下させ、炎症を防ぎます。物理療法を効果的に行うためには、それぞれの治療の適応を十分に把握することが大切です。
家屋調査
家屋調査では、実際に患者さんの自宅や周辺地域の確認をして、リハビリプログラムの作成に役立てます。患者さんや家族とのやり取りだけでは不明瞭な自宅の状況を実際に確認できるため、どの場所でどのような注意が必要なのかが明確となりやすいです。
自宅の退院を本格的に目指すタイミングで行うことが多く、必要に応じて家屋の改修や生活動作の指導も行います。患者さんの身体機能がある程度改善していれば、一緒に自宅に同行して実際の動きを確認することもあります。
他職種との連携
患者さんとのリハビリだけでなく、他職種との連携を頻繁に行うことも理学療法士の大切な仕事です。患者さんを退院までサポートするには理学療法士だけでなく、医師や看護師、ソーシャルワーカーなどの力が必要不可欠です。そのためそれぞれの職種の専門性を活かしつつ、必要な情報は常に共有しておかなければいけません。
また他職種以外にも、家族とのコミュニケーションも重要です。患者さんの退院後の支援内容や、気をつけるべき点について家族に指導することも多いです。
理学療法士が取得しておきたい資格
理学療法士は他の種類の資格を取得することで、仕事や今後のキャリアが有利になるケースがあります。ここでは理学療法士が取得しておきたい資格の一覧をご紹介します。
認定理学療法士
認定理学療法士とは、特定の専門分野の知識・技術の保有が認められた場合に取得できる資格です。認定理学療法士には脳卒中や運動器、神経筋障害などのさまざまな専門分野があり、そのなかから選択します。認定理学療法士の取得方法は、以下の条件があります。
・新人教育プログラムを終了している
・専門分野登録後2年以上が経過している
・特定の研修会を受講している
・研修や学会の参加で得られるポイントが一定以上である
など
これらの条件を満たした後に行われる認定試験を受験して、合格すれば認定理学療法士の資格の取得が可能です。認定理学療法士を取得することで、他の理学療法士との差別化ができるほか、職場によっては手当が出ることもあります。
日本理学療法士協会によると、認定理学療法士の取得者数は2022年6月1日の段階で16,823名。[1] 協会に所属している理学療法士が13万人を超えていることから、その希少性がわかります。
引用:各資格の取得状況|生涯学習 - 公益社団法人 日本理学療法士協会
専門理学療法士
専門理学療法士は認定理学療法士と同じように、専門分野の知識や技術を高めた理学療法士が取得できる資格です。専門理学療法士は認定理学療法士より上位の資格でもあり、より高いスキルが求められます。資格の取得方法は以下のとおりです。
・新人教育プログラムを終了している
・設定されている専門分野から1つ以上を登録する
・専門分野の登録から5年以上経過する
・認定試験申請に必要なポイントを一定以上集める
など
これらの条件を満たした後に認定審査に合格すれば、専門理学療法士の資格を得られます。日本理学療法士協会によると、専門理学療法士の取得者数は4,188名といわれており、認定理学療法士以上に少ないことがわかります。そのため、理学療法士として希少価値の高い人材となりやすいです。
引用:各資格の取得状況|生涯学習 - 公益社団法人 日本理学療法士協会
心臓リハビリテーション指導士
心臓リハビリテーション指導士は、心疾患の再発を防ぐためのリハビリや食事療法、生活指導などの面で役に立つ資格です。心臓リハビリテーション指導士の資格を取得するためには、以下の条件が必要です。
・特定の講習会を受講する
・理学療法士を含めた医療職の資格を取得している
・心臓リハビリテーション学会の会員として2年以上経過している
・心臓リハビリの指導経験が1年以上ある
・心臓リハビリに関係する症例報告を10件作成する
など
これらの条件を満たした後に行う筆記試験に合格すれば、心臓リハビリテーション指導士として認定されます。心臓に関係した専門的な知識・技術を習得している証拠になるので、勤務先が循環器を中心としている場合はこの資格が強みとなります。
呼吸認定療法士
呼吸療法認定士は、呼吸療法を行う人材が少ないという問題を解決するために作られた資格です。患者さんに対して正しい知識を身につけ、正確な呼吸療法を行ってもらうことを目的としています。呼吸認定療法士の認定試験を受けるためには、以下の条件が必要です。
・理学療法士や看護師の経験を2年以上持っている
・学会や講習会の出席で得られる点数を一定数保有している
呼吸認定療法士の資格を持っていると、呼吸器系の診療科を持つ病院の転職では有利となります。その他にも、人工呼吸サポートチームのある病院では貴重な人材としてあつかわれることも多いです。
認知症ケア専門士
認知症ケア専門士は、認知症患者に対する知識やケアを行う技術を養成して、保健・福祉に貢献することを目的とした資格です。認知症ケアに関連した機関で、受験年より10年以内に3年以上の実務経験があれば受験資格を得られ、それ以外の条件はありません。
高齢化社会が進んでいる今、認知症ケアは非常に需要が高いです。そのため、認知症ケア専門士の資格を取得した理学療法士は、どの医療機関においても貴重な人材となりやすいでしょう。資格の条件も比較的やさしいので、認知症に興味がある人はぜひ取得を目指してみましょう。
理学療法士になるための資格を取得しよう
理学療法士は国家資格であり、養成校で3年以上勉強したうえで国家試験に合格する必要があります。資格取得後の勤務先にはさまざまな種類があるため、理学療法士として活躍する場面は多いといえます。また今後も理学療法士として成長していくには、他の資格の取得も視野に入れておく必要もあるでしょう。理学療法士の資格を目指している人は、ぜひ取得後の未来まで見据えたうえで勉強に取り組んでみましょう。関連記事
関連ジャンル
最新コラム記事
-

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
-

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
-

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
-

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
-

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
-

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説
理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説