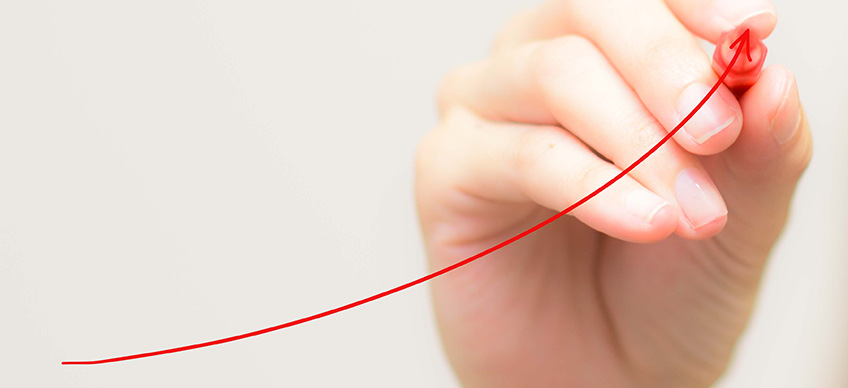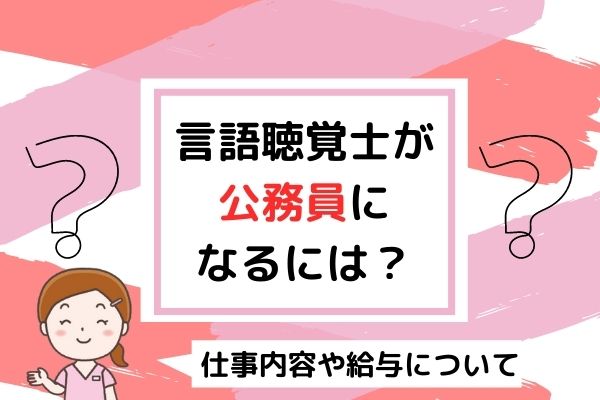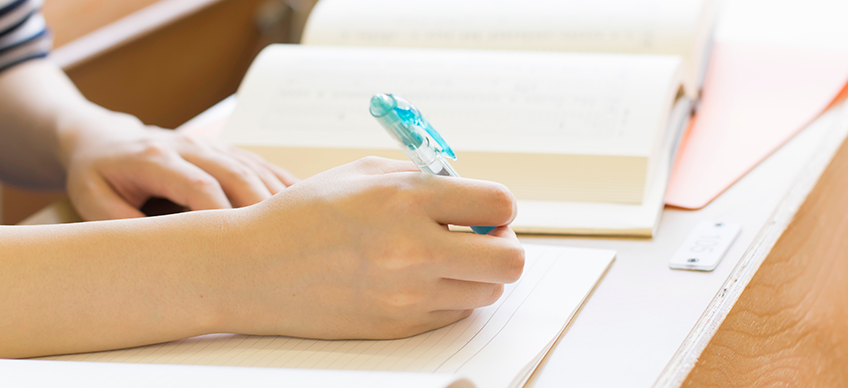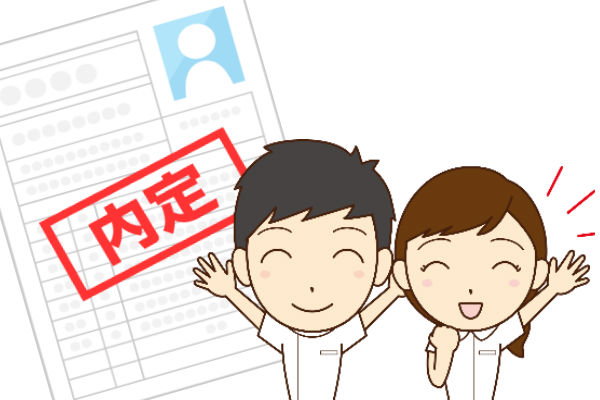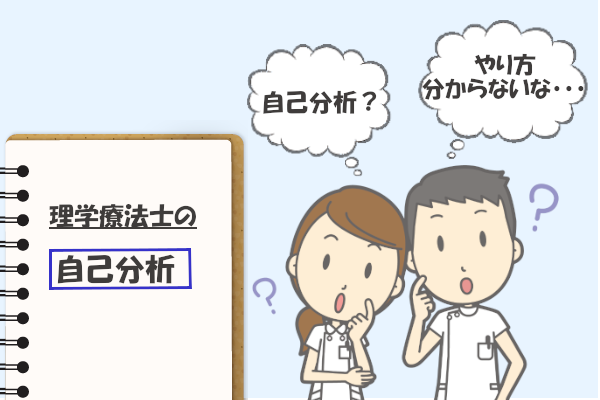廃用症候群のリハビリはどのようにしたら良い?ガイドラインやプログラムについてもご紹介
廃用症候群のリハビリはどのようにしたら良い?ガイドラインやプログラムについてもご紹介
更新日:2023年02月09日
公開日:2023年01月31日

廃用症候群になった場合、リハビリの方法や計画に苦労するかと思います。廃用症候群は元の状態に戻すのは難しいため、予防的な観点でのリハビリが大切です。
今回は、廃用症候群のリハビリ方法やプログラムについて解説しました。また、廃用症候群の患者さんを担当したときに困る内容についても一覧でまとめました。ぜひ、日々の仕事に困った場合は、読んで実践してみてください。
目次
そもそもなぜ起こる?廃用症候群の原疾患とは?
廃用症候群の症状はさまざまです。筋萎縮、骨委縮、心機能低下、うつ状態など心身に関わる不調が現れます。原因となる原疾患は人によって違うため、判断も難しい病気です。
心身の不調の症状がどうして起こってしまうか、その原因について解説します。
廃用症候群はなぜ起こる
廃用症候群が起きる原因としては、身体を動かさないことが1つの原因です。例えば高齢者であれば、筋肉の伸び縮みをしないと1週間に役10∼15%の筋力が落ちてしまいます。身体を動かさないことで、人間の活動機能が低下してしまうのです。
廃用症候群が進んでいくと、最悪の場合は寝たきりの状態になってしまいます。そのため、予防としておこなうリハビリや、症状を無くすための薬物療法等が大切になってきます。
病院でおこなう廃用症候群のリハビリテーションの概要
病院としては、廃用症候群の治療としてリハビリや薬物療法をしてもらいます。寝たきりの状態になる恐れがある方には、寝たきりの状態にならないような運動やリハビリをおこないます。ここでは、実際のリハビリの料金や期間の概要について解説していきます。料金
病院でのリハビリの料金は、何回リハビリを受けたかによって変わってきます。
基本的には、厚生労働省が定めている施設基準によって計算されます。それぞれの点数は以下のとおりです。
1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 180点
2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 146点
3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 77点
「引用:https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/552」
期限
廃用症候群のリハビリテーションの起源は120日です。注意していただきたいのは、病名が診断されてからではなく、「〇〇の廃用症候群」と診断されてから数え始めます。
また、状況によってはリハビリが120日を超えても継続することもあります。主治医の判断によって継続するかどうか決められます。
こんな時どうする?起算日や算定で迷ったときには?
実際に廃用症候群の患者さんを持っている場合、さまざまな聞きなれない単語で悩むことも多いと思います。また、厚生労働省のガイドラインも2年に1度改訂されるため悩むことも多いですよね。
そこで、ここでは廃用症候群のリハビリを考える際に良く悩むポイントについてまとめました。最新の令和4年度版の情報で載せてありますので、ぜひ参考にしてみてください。
算定
算定する場合には、別紙にて毎月評価報告書を作成しないといけません。そのため、厚生労働省にて、作成されている様式を確認しておきましょう。また、算的できる期間は以下のようになっていますので、参考にしてみてください。| 早期リハビリテーション加算 | 廃用症候群に先行する急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は廃用症候群の急性増悪から30日 |
| 初期加算 | 廃用症候群に先行する急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は廃用症候群の急性増悪から14日 |
病名
病名に関しては、基準を用いて算定する必要があります。多く困っているケースとしては、病名欄の書き方です。「肺炎による長期伏床による廃用症候群」などと、書く場合には廃用症候群を書くようにしましょう。また、長く書くことが難しい場合には、詳記にて経路を書くようにしましょう。レセプト
レセプトとは、診療報酬明細書のことです。どのような診療をしてもらい、料金を払っているかを詳細に記述したものです。厚生労働省から出されている、基準に基づいて計算します。
例えば、120日の期限が過ぎた場合のレセプトは、そのつど確認して記入する必要があります。自分だけの判断になってしまうと、間違える危険性があるので、担当になっている医者の指示を確認しておくと良いでしょう。
回復期
廃用症候群リハビリテーション科と、回復期リハビリテーション科は別になっています。そのため、どちらの病棟として算定するかは悩ましいかと思います。
通常の廃用症候群は「急性疾患等に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの」とされています。
「回復期リハビリテーションを要する状態」の廃用症候群は、「外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(手術後又は発症後2か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。)」となっています。そのため、本人の症状に合わせて選ぶようにしましょう。
起算日
起算日とは、病名の治療が開始された日のことを指します。そのため、廃用症候群は原疾患の病気と、廃用症候群か区別がつきづらくなっています。
ポイントとしては、早期リハビリテーション加算と初期加算を確認することです。どちらも、急性疾患の発症、もしくは急性増悪からの期間が決められています。そのため、期日を確認しておくと良いでしょう。
実際に使える廃用症候群のリハビリテーションのフプログラムとは?
廃用症候群の方には、それ以上悪化させないためにリハビリを進めていきます。しかし、症状がひとによって様々なため、個別の計画を立てるのは難しいことです。
今回はそんな方に向けて、効果があるプログラムについてご紹介します。参考にしていただき、ぜひご自身の患者さんのリハビリ計画で試してみてください。
廃用症候群のガイドラインとは?
廃用症候群のガイドラインは、厚生労働省からは出されていません。そのため、学会や論文で発表されているものが主なガイドラインとなっております。日本理学療法士協会では、会員だと理学療法ガイドラインを閲覧できます。ぜひ参考にしてみてください。
参照:https://www.japanpt.or.jp/info/20220420_563.html
実際に使えるプログラムのご紹介
廃用症候群では、プログラムはお医者さんとの相談で決めています。そのため、個人の状況によって、プログラムの内容は変化します。そこで、ここでは、実際のプログラムでおこう事が多い3つのリハビリを紹介します。
1つ目は、関節可動域訓練です。第3者と一緒に関節を動かしていくリハビリです。廃用症候群になると、どうしても動かすのが大変になってしまいます。そのため、第3者が動かすことによって固まってしまった関節をほぐしていきます。
2つ目はレクリエーションです。遊びをすることによって意欲的に活動を増やす方法です。どうしても気もちが沈んでしまうことが多いので、楽しく意欲的に過ごせるレクリエーションは、プログラムに組み込まれます。
3つ目はポジショニングです。ベットに寝たきりになっている患者さんにおこないます。関節の拘縮や浮腫などを緩和させる方法であり、ベッドに寝たきりになって起こる負担を減らせます。
まとめ
廃用症候群のリハビリについてまとめました。廃用症候群は、実際に進行してしまうと元の状態に戻していくのが難しい病気です。あせらず長期的な視点で見ていけると良いでしょう。
また、レセプトなど算定日などが分からなくなることが多くあります。今回載せたのは一例ですので、患者さんの状況によって書き方は変わってきます。担当医などに確認をしながら進めていくようにしてください。
関連記事
関連ジャンル
最新コラム記事
-

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
-

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
-

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
-

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
-

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
-

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説
理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説