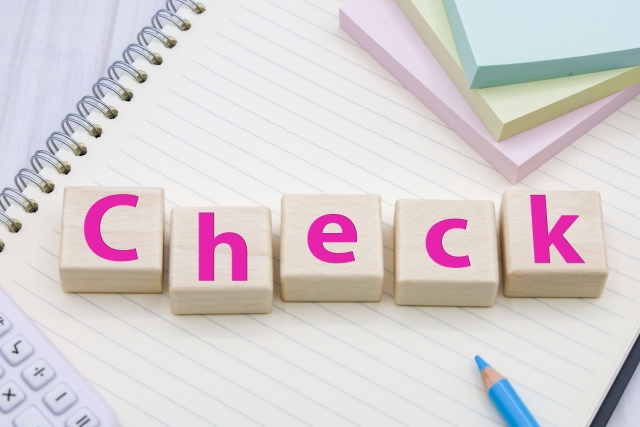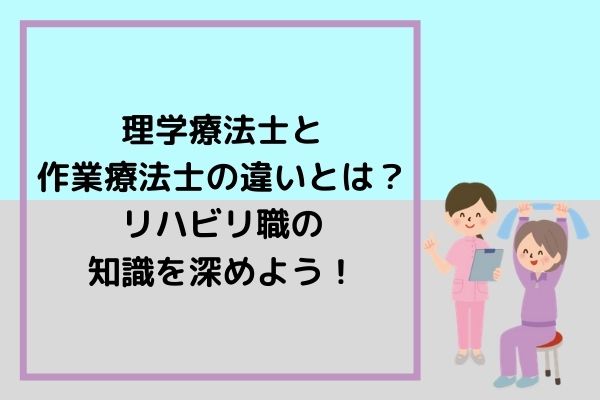通所リハビリテーションとは?実施する内容や利用時のメリットについて解説
通所リハビリテーションとは?実施する内容や利用時のメリットについて解説
更新日:2023年02月22日
公開日:2023年02月22日

親の健康のために通所リハの利用をすすめられたものの、どんなサービスなのかいまいちわからない方は多いのではないでしょうか。通所リハはリハビリに特化した介護保険サービスであり、その他にも入浴や食事なども行ってくれます。この記事では通所リハの内容や利用するメリットなどについてご紹介します。通所リハの概要をおさえたうえで、ぜひ利用を検討してみましょう。
目次
通所リハビリテーションとは?
通所リハビリテーションとは、老人保健施設や病院に通って運動、食事、入浴などを受けられる介護保険サービスです。おもに「通所リハ」や「デイケア」と呼ばれています。通所リハには医師やリハビリスタッフ、看護師などの職員が在籍しており、体調の管理や専門的なリハビリを受けられるのが特徴です。通所リハでは生活支援だけでなく、必要に応じて住宅改修や福祉用具のアドバイスも行います。通所リハビリテーションの1日の流れ
ここでは通所リハを利用する方の1日の流れについてご紹介します。
1.自宅から送迎車を利用して施設に移動
2.看護師によるバイタルチェックを実施
3.希望者の入浴介助を実施
4.リハビリを実施
5.昼食
6.ゲームや体操などのレクリエーションを実施
7.送迎車を利用して施設から帰宅
通所リハはスタッフが自宅から施設まで送迎してくれるので、本人や家族の負担をかけにくいのが利点です。リハビリは個別での指導の他に、運動器具の使用や集団での体操も行います。
通所リハビリテーションとデイサービスとの違い
通所リハに似たようなサービスには「デイサービス」があります。これらのサービスにはどのような違いがあるのかを解説します。通所リハとデイサービスのおもな違いは、以下の3つです。
● 提供するサービスの目的の違い
● 在籍しているスタッフの違い
● リハビリ内容の違い
通所リハビリのサービスは「身体機能の維持・改善」や「コミュニケーション能力の向上」などが目的です。一方、デイサービスは「心身の健康維持」や「社会的交流を設ける場」などが目的です。
またデイサービスには、必ず理学療法士や作業療法士といったリハビリスタッフが在籍しているわけではありません。そのため、看護師や柔道整復師などの職種が運動・体操を担当する関係上、専門的なリハビリを行えないこともあるでしょう。身体機能の改善のために専門的なリハビリを受けたい方は、通所リハがおすすめです。
通所リハビリテーションが利用できる対象者
ここでは通所リハを利用できる対象者について解説します。通所リハは「要支援1〜2」あるいは「要介護1〜5」の認定を受けている方が利用できます。要介護の認定条件は、基本的に65歳以上でなければいけませんが、40〜64歳で特定疾患を抱えている方でも申請が可能です。要支援・要介護の認定を持っていない場合は、まずは市区町村の役所で申請をしましょう。
通所リハビリテーションの費用
ここでは通所リハの費用の目安についてご紹介します。
| 1〜2時間 | 2〜3時間 | 3〜4時間 | 4〜5時間 | 5〜6時間 | 6〜7時間 | 7〜8時間 | |
| 要介護1 | 331円 | 345円 | 446円 | 511円 | 579円 | 670円 | 716円 |
| 要介護2 | 360円 | 400円 | 523円 | 598円 | 692円 | 801円 | 853円 |
| 要介護3 | 390円 | 457円 | 599円 | 684円 | 803円 | 929円 | 993円 |
| 要介護4 | 419円 | 513円 | 697円 | 795円 | 935円 | 1,081円 | 1,157円 |
| 要介護5 | 450円 | 569円 | 793円 | 905円 | 1,065円 | 1,231円 | 1,317円 |
(※1回あたりの金額)
| 1月につき | |
| 要支援1 | 1,721円 |
| 要支援2 | 3,634円 |
これらの金額はあくまでも目安であり、通所リハの規模や地域によって費用が変動します。その他にも「リハビリテーションマネジメント加算」や「入浴介助加算」などの別途費用がかかる場合もあります。
通所リハビリテーションを利用するメリット
通所リハの活用は、利用者にとってさまざまな利点があります。ここではおもなメリットについて解説します。
リハビリの専門職がいる
なによりも理学療法士や作業療法士などのリハビリスタッフがいる点が、通所リハの最大のメリットです。通所リハでは、1名以上のリハビリスタッフの配置が条件としてつけられています。そのため、リハビリスタッフによる専門的な指導を受けられます。
自宅の過ごし方で悩みがある際は家屋調査を行い、環境にあわせたリハビリの提案や福祉用具の選定もしてくれるでしょう。通所リハには医師と看護師もいるので、運動時に体調が悪くなったときでも、すぐに診察や処置もしてくれます。
定期的に身体機能の評価をしてくれる
通所リハでは専門的なリハビリを行えるだけでなく、定期的に身体機能の評価もしてくれます。通所リハを利用することで、身体機能にどのような変化があるのかは気になるのではないでしょうか。理学療法士や作業療法士はリハビリを行うだけでなく、筋力やバランス、日常生活動作の評価を行うことも仕事のひとつです。
そのため、通所リハを利用した結果、身体機能がどのように改善したのかがわかります。以前よりも身体機能が改善したと自覚できたら、利用者本人も運動に対してのモチベーションがさらに高まるでしょう。
リハビリに必要な器具がそろっている
通所リハはリハビリに特化したサービスでもあるため、運動に必要な器具が充実しているのも大きなメリットです。リハビリ器具がそろっていれば運動の効果が高まるだけでなく、自主トレーニングを行う際にも役立つでしょう。リハビリ器具には、以下のようなものがあります。
● 平行棒
● 重錘(重り)
● エルゴメーター
● トレッドミル
● バランスボール など
このように、通所リハはリハビリを行うにあたって最適な環境であることがわかります。
通所リハビリテーションを利用する際の注意点
通所リハの利用に特別なデメリットはありませんが、気をつけるべきポイントがいくつかあります。ここでは通所リハを利用するにあたっての注意点について解説します。
利用に時間がかかる
通所リハは手続きのための準備に時間がかかるので、すぐに利用できるわけではありません。通所リハを利用するためには、以下の書類の作成が必要です。
● 診療情報提供書
● 健康診断書
これらは主治医が作成する書類であり、一番手間なのが健康診断書です。事前に健康診断を受ける必要があり、場所によっては書類が完成するまで時間がかかることもあるでしょう。デイサービスでは健康診断書の提出が不要な場所もあるので、比較すると手間に感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
リハビリスタッフがずっと指導をするわけではない
通所リハでは専門的なリハビリを行えますが、理学療法士や作業療法士がずっと1対1で指導をするわけではありません。リハビリを行う利用者は多くいるので、30分ほど指導を受けた後は自主トレがほとんど、というケースもあるでしょう。
とくに通所リハの利用者が多く、在籍しているリハビリスタッフが少ない場合、さらに1対1の時間が短い傾向にあります。最初からマンツーマンでのリハビリを期待していると、そのギャップに困惑するかもしれません。
施設によってリハビリ器具が異なる
通所リハは効果的なリハビリを行う器具が用意されていますが、すべての施設が同じように充実しているわけではありません。設備が充実していないとリハビリの効果が著しく低下する、というわけではありませんが、運動内容のバリエーションは少なくなるでしょう。通所リハを利用するときは事前に施設の情報をチェックしておくことをおすすめします。
通所リハビリテーションを選ぶときのポイント
通所リハは施設によってそれぞれ特徴が異なります。ここでは通所リハを選ぶときのポイントについて解説します。
利用条件にあった施設を選ぶ
通所リハを利用する際に求めている条件に適した施設を選びましょう。たとえば、以下のような条件があります。
● 送迎が開始する時間
● 施設までの乗車時間
● 利用者の総人数
● 通所リハのサービス時間
● 入浴介助が可能な範囲
● 食事量や食事形態の調節
● トラブルが起きた際の対応 など
このように、家族の都合と利用者本人の状態にあったサービスなのかを確認します。場合によっては通所リハ以外のサービスを利用した方がいいケースもあるので、求める条件を書き出してみましょう。
リハビリ環境が整っているか確認する
施設の設備はもちろん、リハビリスタッフが充実しているかを確認しましょう。リハビリ職には理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がおり、それぞれ役割が異なります。すべての通所リハにそれぞれのリハビリ職がいるわけではないので、希望する職種が在籍しているかを把握しておくことは大切です。
また、リハビリスタッフの在籍人数も重要な要素です。リハビリスタッフが多ければ、その分マンツーマンでじっくり指導を受けられる時間は増えるでしょう。リハビリが目的で利用する場合は、優先して確認すべきポイントです。
施設の雰囲気も確認しておく
通所リハの雰囲気が、利用者本人とマッチしているかを確認することも大切です。もしスタッフの対応や利用者同士の雰囲気が悪い場合、本人が通所リハに行くのを途中でやめてしまう可能性もあります。雰囲気をしっかりとチェックするためにも、なるべく利用予定の本人と一緒に見学しましょう。
とくにレクリエーションの時間や余暇時間は、利用者同士の雰囲気が伝わりやすいです。通所リハのスケジュールをスタッフに確認して、見学したい時間帯に訪れてみましょう。
通所リハビリテーションに在籍する職種の役割
通所リハにはさまざまな種類の職種が在籍しており、専門性を活かしたサポートを提供しています。ここではそれぞれの職種の役割についてご紹介します。
医師
医師は理学療法士や作業療法士にリハビリ内容を指示したり、利用者に対しての注意点などを伝えたりします。また、必要に応じて医療ケアを実施することもあります。
看護師
看護師はおもに利用者のバイタルチェックや服薬の管理が中心です。利用者の状態によってはインスリン注射やバルーンカテーテルの管理といった医療処置を実施します。リハビリの補助として、利用者の歩行介助を行ったりマシンへ誘導したりすることもあります。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士では、それぞれの役割にあわせたリハビリを実施します。理学療法士は歩いたり立ったりなどの、日常で使用する基本的な動きの獲得を中心にリハビリを行う職種です。作業療法士は基本的な動きだけでなく、仕事や趣味で使用するような応用的な動作の獲得も目指します。
理学療法士と作業療法士は、具体的に筋力トレーニングや可動域訓練、応用動作訓練などを行います。言語聴覚士は「聞く・しゃべる」といった、コミュニケーション手段と食事に関する機能の改善を目指す職種です。発声の練習や飲み込みの練習などを行うのが言語聴覚士の特徴です。
介護士
介護士は食事や入浴、トイレ介助を中心に行います。施設によってはリハビリマシンへの誘導や、集団でのレクリエーションを担当することもあります。送迎車を運転して、利用者の送り迎えを行う役割を担っていることも多いです。
このように、それぞれの職種が連携しながら通所リハのサービスを提供しているのです。
通所リハビリテーションの利用時に準備するもの
ここでは通所リハを利用することになった際に準備するものについてご紹介します。準備が必要なものは以下のとおりです。
● 保険証
● 生活必需品 など
介護保険証や負担割合証など、その人にあわせた保険証は必ず用意しておきましょう。生活必需品には着替えや歯ブラシ、上履きなどがあげられます。また内服薬を持参したり、通所リハごとに必要なものを用意したりなど、利用者や施設にあわせて持ち物を準備しましょう。
通所リハビリテーションの仕組みや費用をおさえておこう
通所リハはデイサービスと同じようなサービスに思われがちです。しかしリハビリ職が在籍していたり、リハビリに特化していたりなど、デイサービスより機能的なアプローチを行えます。リハビリのための設備も充実していることが多いため、運動を希望している本人や家族にはおすすめです。通所リハによって環境がそれぞれ異なるため、事前に施設内の見学を行うことが大切です。親にいつまでも健康に過ごしてもらうためにも、ぜひ通所リハを活用してみましょう。
関連記事
関連ジャンル
最新コラム記事
-

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
-

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
-

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
-

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
-

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
-

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説
理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説