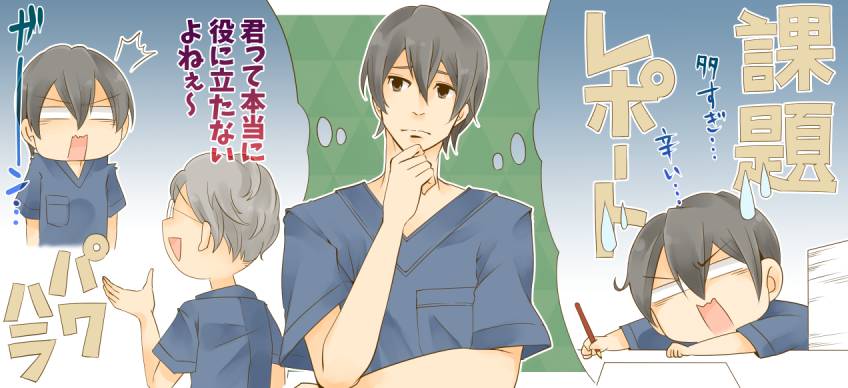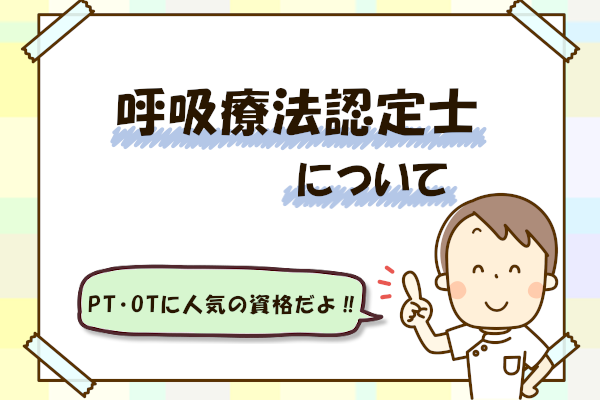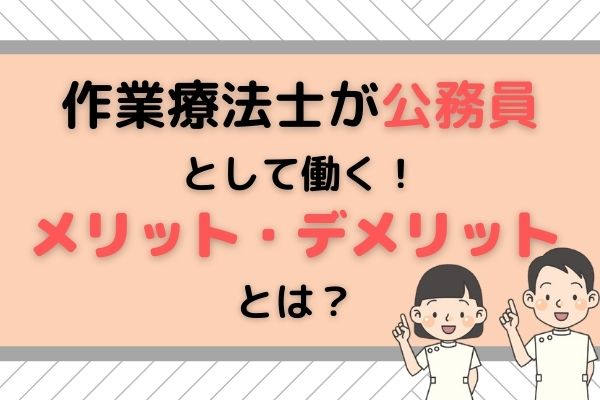「疾患別リハビリテーション料」とは、脳血管疾患等リハビ料や運動器リハビリ料などをまとめて表したものです。疾患別リハビ料では、疾患ごとに対象や点数、施設基準が異なるので、それぞれをおさえておく必要があります。この記事では、疾患別リハビリ料を項目別に分けながら解説していきます。予定しているリハビリ料を算定するためにも、その詳細を把握しておきましょう。
目次
疾患別リハビリテーション料とは
疾患別リハビリテーション料とは、さまざまな疾患に対応したリハビリ料をまとめて指した言葉です。以下の5種類に分類されます。
● 心大血管疾患リハビリ料
● 脳血管疾患等リハビリ料
● 廃用症候群リハビリ料
● 運動器リハビリ料
● 呼吸器リハビリ料
それぞれの対象疾患は以下の通りです。
【心大血管疾患リハビリ料】
● 急性心筋梗塞
● 狭心症
● 開心術後
● 大血管疾患(大動脈解離、解離性大動脈瘤など)
● 慢性心不全 など
【脳血管疾患等リハビリ料】
● 脳梗塞
● 脳出血
● くも膜下出血
● 脳腫瘍
● 脊髄損傷
● パーキンソン病
● 高次脳機能障害 など
【廃用症候群リハビリ料】
● 急性疾患にともなう安静による廃用症候群
【運動器リハビリ料】
● 上・下肢の複合損傷
● 脊椎損傷による四肢麻痺
● 運動器の悪性腫瘍 など
【呼吸器リハビリ料】
● 肺炎・無気肺
● 肺腫瘍
● 肺塞栓
● 慢性閉塞性肺疾患 など
引用:令和4年度診療報酬改定の概要
疾患別リハビリテーション料の点数と算定日数
ここでは、疾患別リハビリ料の点数や算定日数などについて解説します。それぞれ施設基準によって2〜3種類に区分され、それに応じて点数が異なります。心大血管疾患リハビリテーション料
● 心大血管疾患リハビリ料(Ⅰ):205点/単位
● 心大血管疾患リハビリ料(Ⅱ):125点/単位
標準的算定日数は150日。
脳血管疾患等リハビリテーション料
● 脳血管疾患等リハビリ料(Ⅰ):245点/単位
● 脳血管疾患等リハビリ料(Ⅱ):200点/単位
● 脳血管疾患等リハビリ料(Ⅲ):100点/単位
標準的算定日数は180日。
廃用症候群リハビリテーション料
● 廃用症候群リハビリ料(Ⅰ):180点/単位
● 廃用症候群リハビリ料(Ⅱ):146点/単位
● 廃用症候群リハビリ料(Ⅲ):77点/単位
標準的算定日数は120日。
運動器リハビリテーション料
● 運動器リハビリ料(Ⅰ):185点/単位
● 運動器リハビリ料(Ⅱ):170点/単位
● 運動器リハビリ料(Ⅲ):85点/単位
標準的算定日数は150日。
呼吸器リハビリテーション料
● 呼吸器リハビリ料(Ⅰ):175点/単位
● 呼吸器リハビリ料(Ⅱ):85点/単位
標準的算定日数は90日。
算定日数上限を超えた場合のリハビリについて
疾患別リハビリ料にはそれぞれ算定日数が設けられており、その期間を過ぎると算定が行えません。しかし、日数の上限を超えても、治療の継続で状態の改善が見込めると判断された場合は、1か月13単位に限って算定が可能です。このとき、算定日数の上限を超えた対象者が要介護被保険者だと、以下の疾患リハビリ料の点数が変わります。
● 脳血管疾患等リハビリ料
● 廃用症候群リハビリ料
● 運動器リハビリ料
それぞれのリハビリ料の点数は以下の通りです。
【脳血管疾患等リハビリ料】
● 脳血管疾患等リハビリ料(Ⅰ):147点/単位
● 脳血管疾患等リハビリ料(Ⅱ):120点/単位
● 脳血管疾患等リハビリ料(Ⅲ):60点/単位
【廃用症候群リハビリ料】
● 廃用症候群リハビリ料(Ⅰ):108点/単位
● 廃用症候群リハビリ料(Ⅱ):88点/単位
● 廃用症候群リハビリ料(Ⅲ):46点/単位
【運動器リハビリ料】
● 運動器リハビリ料(Ⅰ):111点/単位
● 運動器リハビリ料(Ⅱ):102点/単位
● 運動器リハビリ料(Ⅲ):51点/単位
このように、要介護被保険者は本来のリハビリ料よりも低い点数で算定されます。
引用:令和4年度診療報酬改定の概要
第 7部 リハビリテーション 通則
疾患別リハビリテーション料に係る施設基準
疾患別リハビリ料を算定するためには、スタッフやリハビリ施設環境を一定の水準に満たす必要があります。ここでは、それぞれの区分に必要な施設基準について解説します。
心大血管疾患リハビリテーション料
【心大血管疾患リハビリ料(Ⅰ)】
● 循環器科または心臓血管外科の医師が実施時間帯に常時勤務
● 専任の常勤医師が1名以上
● 専従の常勤理学療法士(PT)および看護師があわせて2名以上
● 必要に応じた作業療法士(OT)の配置
● 病院の専有面積は30㎡以上、診療所の場合は20㎡以上
● リハビリに必要な器械・器具が用意されている
【心大血管疾患リハビリ料(Ⅱ)】
● 非常勤を含む1名以上の医師が実施時間帯に勤務
● 専従のPTまたは看護師いずれか1名以上
● 必要に応じたOTの配置
● 病院の専有面積は30㎡以上、診療所の場合は20㎡以上
● リハビリに必要な器械・器具が用意されている
脳血管疾患等リハビリテーション料
【脳血管疾患等リハビリ料(Ⅰ)】
● 専任の常勤医師が2名以上
● 専従のリハビリスタッフが合計10名以上
● 専従の常勤PTが5名以上
● 専従の常勤OTが3名以上
● 言語聴覚療法を行う場合、専従常勤の言語聴覚士(ST)が1名以上
● 専有面積が160㎡以上
● リハビリに必要な器械・器具が用意されている
【脳血管疾患等リハビリ料(Ⅱ)】
● 専任の常勤医師が1名以上
● 専従のリハビリスタッフが合計4名以上
● 専従の常勤PTが1名以上
● 専従の常勤OTが1名以上
● 言語聴覚療法を行う場合、専従常勤の言語聴覚士(ST)が1名以上
● 専有面積は病院なら100㎡以上、診療所なら45㎡以上
● リハビリに必要な器械・器具が用意されている
【脳血管疾患等リハビリ料(Ⅲ)】
● 専任の常勤医師が1名以上
● 専従の常勤PT・OT・STのいずれかが1名以上
● 専有面積は病院なら100㎡以上、診療所なら45㎡以上
● リハビリに必要な器械・器具が用意されている
例外として、言語聴覚療法のみを実施する場合は、上記の基準ではなく以下の条件を満たすだけで算定が可能です。
【脳血管疾患等リハビリ料(Ⅰ)の場合】
● 専任の常勤医師が1名以上
● 専従の常勤STが3名以上
● リハビリに必要な器械・器具が用意されている
【脳血管疾患等リハビリ料(Ⅱ)の場合】
● 専任の常勤医師が1名以上
● 専従の常勤STが2名以上
● リハビリに必要な器械・器具が用意されている
また言語聴覚療法を実施する際は、8㎡以上の専用室が1室以上必要
廃用症候群リハビリテーション料
廃用症候群リハビリ料の施設基準は、脳血管疾患等リハビリ料の条件に準じます。脳血管疾患リハビリ料(Ⅰ〜Ⅲ)の施設が満たされていれば、廃用症候群リハビリ料(Ⅰ〜Ⅲ)の算定が可能です。
運動器リハビリテーション料
【運動器リハビリ料(Ⅰ)】
● 専任の常勤医師が1名以上
● 専従の常勤PT・OTあわせて4名以上
● 専有面積は病院なら100㎡以上、診療所なら45㎡以上
● リハビリに必要な器械・器具が用意されている
【運動器リハビリ料(Ⅱ)】
● 専任の常勤医師が1名以上
● 専従の常勤PTが2名またはOTが2名以上、あるいはPT・OTあわせて2名以上
● 専有面積は病院なら100㎡以上、診療所なら45㎡以上
● リハビリに必要な器械・器具が用意されている
【運動器リハビリ料(Ⅲ)】
● 専任の常勤医師が1名以上
● 専従の常勤PTまたはOTが1名以上
● 専有面積が45㎡以上
リハビリに必要な器械・器具が用意されている
呼吸器リハビリテーション料
【呼吸器リハビリ料(Ⅰ)】
● 専任の常勤医師が1名以上
● 専従の常勤PT1名を含んだうえで常勤PT・OT・STあわせて2名以上
● 専有面積は病院なら100㎡以上、診療所なら45㎡以上
● リハビリに必要な器械・器具が用意されている
【呼吸器リハビリ料(Ⅱ)】
● 専任の常勤医師が1名以上
● 専従の常勤PT・OT・STが1名以上
● 専有面積が45㎡以上
● リハビリに必要な器械・器具が用意されている
引用:令和4年度診療報酬改定の概要
疾患別リハビリテーション料の算定要件
疾患別リハビリ料の算定要件は、令和4年度の診療報酬の改定によって内容が新しくなりました。診療報酬の改定で重視された点は、FIM(機能的自立度評価法)の測定です。算定日数を超えてリハビリを実施する際は、FIMの測定が条件となりました。これは質の高いリハビリを推進するために追加されたものと考えられます。具体的な内容は以下の通りです。
● 1か月に1回以上、FIMを測定して患者のリハビリの必要性を判断する
● 作成したリハビリ実施計画書を患者または家族に説明したうえで交付し、写しを診療録に添付する
● 1年間で疾患別リハビリ料を算定した患者の人数やFIMなどの報告を行う
その他にも「リハビリ実施計画書」および「リハビリ実施総合実施計画書」の署名についても変更があります。これまでは患者様や家族の署名が必要でしたが、住まいや本人の事情によって直接記載がむずかしいケースがありました。その措置として、患者様や家族へ説明したうえで、その旨を診療録に記載すれば署名を行う必要がなくなりました。
このように、制度の改定によってリハビリの質向上を推進しつつ、算定に関する手続きの簡略化が進んでいます。
引用:令和4年度診療報酬改定の概要
疾患別リハビリテーション料に関係する疑義解釈
ここでは疾患別リハビリ料に関係する疑義解釈をご紹介します。
(※以下引用文)
(問201)リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書について、「計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、遠方に居住している等の理由により患者の家族等が署名することが困難である場合には、(中略)家族等に情報通信機器等を用いて計画書の内容等を説明した上で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載することにより、患者又はその家族等の署名を求めなくても差し支えない。ただし、その場合であっても、患者又はその家族等への計画書の交付が必要であること等に留意すること」とあるが、
1 この場合、医師が計画書の内容等の説明等を行う必要があるか。
2 診療録に計画書を添付することをもって、「説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載すること」に代えることはできるか。
3 交付する計画書の署名欄はどのように取り扱えばよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
1 そのとおり。
2 不可。家族等への説明を行った医師による診療録への記載が必要である。
3 当該計画書を作成した医師が、計画書の署名欄に、同意を取得した旨、同意を取得した家族等の氏名及びその日時を記載すること。
(問202) 前問のリハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書の署名の取扱いに関し、「疾患別リハビリテーションを当該患者に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾患別リハビリテーションを実施する場合を含む。)を除き」とあるが、他の保険医療機関から転院した患者であって、転院前から継続して疾患別リハビリテーションを実施するものについては、どのように考えればよいか。
(答)署名の取扱いについては、「疾患別リハビリテーションを初めて実施する場合」に該当するものとして取り扱うこと。
(問203)標準的算定日数を超えて、1月に13単位以内の疾患別リハビリテーションを行っている患者について、1月に1回以上FIMの測定を行う必要があるか。
(答)原則として測定を行う必要がある。
引用:疑義解釈資料の送付について(その1)
疾患別リハビリテーション料の概要を理解しておこう(まとめ)
疾患別リハビリ料は、患者様にリハビリを提供するにあたっておさえておかなければいけない制度です。医療機関によってどのような疾患をどの区分で取り扱うかが異なるので、関係のあるポイントはおさえておきましょう。また疾患別リハビリ料に限らず、制度は今後も定期的に改定されます。そのため、制度の改定にともなった対応力も求められます。現状の疾患別リハビリ料を理解しつつ、今後の制度の動向にも目を向けてみましょう。関連ジャンル
最新コラム記事
-

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
-

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
-

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
-

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
-

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
-

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説
理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説