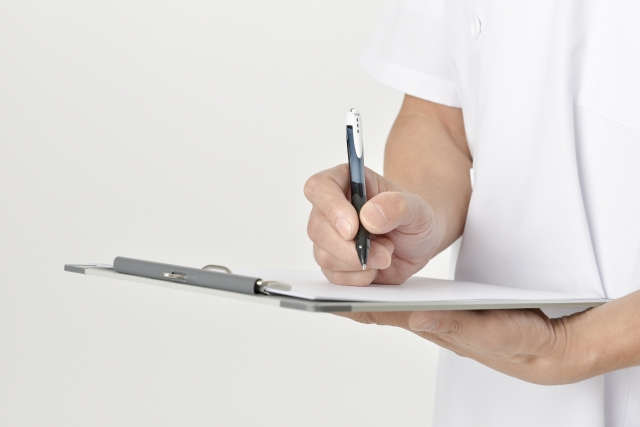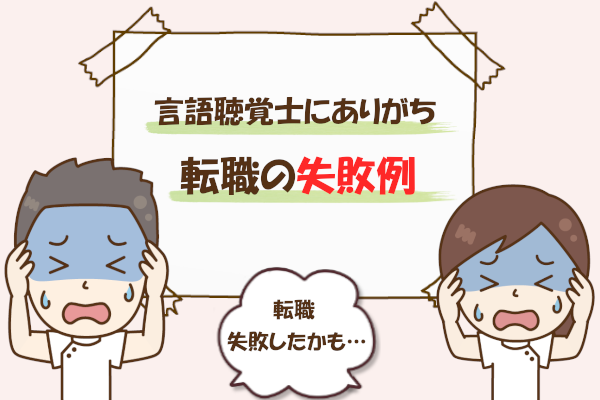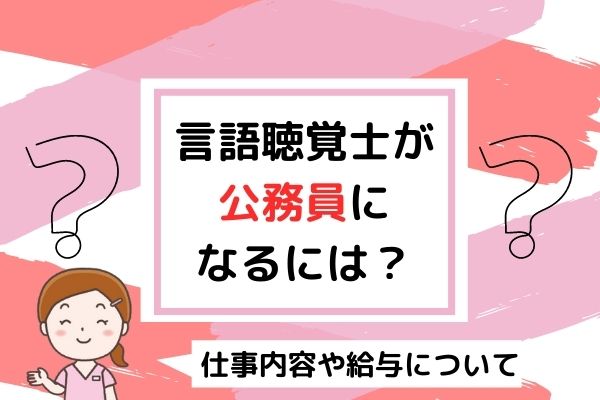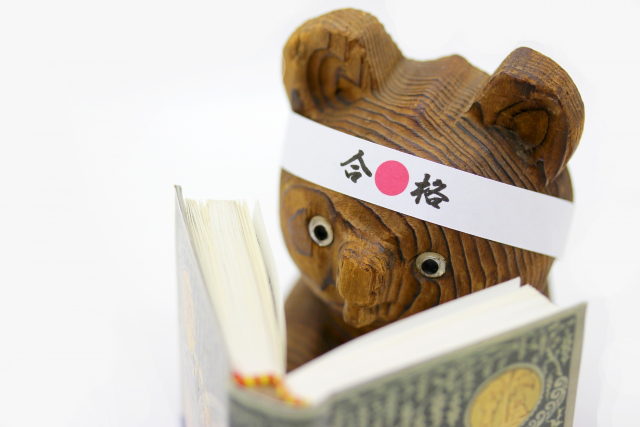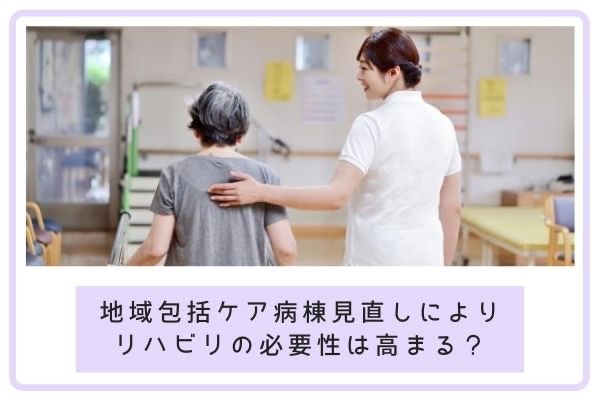交通事故でケガをしたときに、症状や身体機能を治するために整形外科でリハビリ通いをするケースは多いでしょう。一方で、どのタイミングでリハビリをやめれば良いのか、よくわからない方もいるのではないでしょうか。リハビリの期間に明確な答えはなく、その方のケガの具合によって変わります。この記事では、整形外科にいつまで通うべきかについてご紹介します。リハビリ通いをするかどうかの基準やポイントをおさえておけば、適切なタイミングで通院を終了できるでしょう。
目次
整形外科のリハビリにいつまで通うべき?
ケガが原因でリハビリを行う際に、いつまで通うべきなのでしょうか。ここでは通う期間について解説します。
いつまで通うかは人によって異なる
結論をいうと、いつまで整形外科のリハビリに通うべきかに、明確な答えはありません。その方の環境やケガの状況によって異なるからです。たとえば、事故によるケガの程度が強ければ治療までに時間がかかるので、リハビリに通う期間は長くなるでしょう。一方で、ケガや痛みがそこまで重くなければ、短期間でも問題ないケースもあります。
ケガの状況だけでなく、その方の生活背景や家族構成によっても期間は変わります。通う期間に決まった基準はないので、医師と相談しながらリハビリをいつまで続けるかを相談していく必要があるでしょう。
運動器リハビリの期限は150日まで
保険を利用してリハビリを行う場合は、疾患によって一定の期限が設けられています。たとえば、ケガによって骨折をしたら「運動器リハビリテーション」として扱われます。その場合のリハビリ期限は、診断日より150日までです。事故によるケガのほとんどは運動器リハビリの対象なので、ほとんどのケースは150日が期限といえるでしょう。
その他にも、脳出血や脳外傷などの疾患の場合は「脳血管疾患等リハビリテーション」の扱いとなり、180日の期限が設けられます。このように、基本的に150日が期限であることが多いですが、ケガの内容によって期間が変わる場合があります。
整形外科のリハビリに通うかどうかの基準
リハビリ通いをやめるかどうかを考えるとき、どのような点を考慮すべきでしょうか。ここではリハビリを続ける基準について解説します。
症状の種類・程度
最も重要なのが、受傷した際の症状の種類や程度によって、リハビリを続けるどうかを判断する点です。ケガの程度が重かったり、身体の広範囲まで及んでいたりしていれば、リハビリの必要性は高いといえるでしょう。
一方で、症状が落ち着いている、あるいは日常生活に問題がないレベルのケガであれば、整形外科に長期間通う必要性は薄いと考えられます。症状が不安定なうちは、日常生活でどのように影響するかが予測しにくいので、リハビリを通い続けて様子をみておくことをおすすめします。
ケガをした時期
ケガをした時期もリハビリを続けるかどうかの基準のひとつです。ケガをして間もない時期であれば、炎症や痛みが残っている可能性は高くなります。そのため、リハビリを続けて身体機能の改善、損傷部位の回復に専念した方がいいケースもあるでしょう。
ケガをしてからある程度の期間が経過していれば、痛みも落ち着き、身体機能も少しずつ戻っていきます。日常生活を過ごすうえで問題がなければ、リハビリを終了してもいいと考えられます。
ケガをした場所
ケガをした場所によってもリハビリの期間は大きく異なります。たとえば、骨折は基本的に数か月〜半年程度で回復しますが、ケガの場所や程度によってはなかなか治らないケースもあります。 手術を要する場合は、治療期間はまた大きく変わるでしょう。このように、ケガの場所が異なるだけでも日常生活への影響や治療期間が異なる点には注意する必要があります。年齢
年齢によってもリハビリに通う期間は変わります。若い人の方は高齢者と比べると、ケガの治りは速い傾向にあります。 そのため、高齢者ほど治療に時間がかかり、リハビリの期間も長くなるでしょう。また、ケガや身体機能の回復に影響があるのは年齢だけではありません。日常的に運動を行っているか、栄養状態が良好なのかなどの要素も絡んできます。とくに加齢によって筋力や体力が落ちている方がケガをすると、さらに身体機能が落ちてしまうので、リハビリの期間が長引く傾向にあります。
家族構成
ケガをした方の家族構成によっても、リハビリを続けるかどうかの基準になります。たとえば、1人暮らしだとしたら自分だけの力で日常生活を過ごす必要があるでしょう。1人暮らしでは身体機能に不便がないようにする必要があるため、入念にリハビリを行う必要があります。
一方で、自宅に家族が住んでいれば、ある程度のサポートを受けられる可能性があります。状況によっては、早めにリハビリを切り上げることも可能でしょう。ただし、基本的には身体機能の改善の余地があればリハビリを続ける方が望ましいので、家族とよく相談する必要があります。場合によっては別のリハビリサービスの検討をすることも考えておきましょう。
整形外科のリハビリで行う内容
整形外科では、おもに理学療法士と一緒にリハビリを行います。理学療法士はリハビリを行う専門職の1つです。ケガや病気によって身体機能に支障が出た方にリハビリを提供し、今までの生活を送れるように支援するのがおもな役割です。ここでは整形外科のリハビリで何をするのかについて解説します。
運動療法
運動療法は、筋力トレーニングやストレッチ、歩行訓練などを行って身体の機能改善を図るリハビリです。ケガによって低下した筋力や体力を取り戻し、以前までの身体機能に近づけるために運動を行います。運動療法には決まった内容はなく、一人ひとりに適したリハビリを実施します。理学療法士がその方の希望や悩みを聴取し、身体機能の評価を行ったうえで、リハビリプログラムを作成するのが特徴です。
物理療法
物理療法は、熱や超音波、電気などのエネルギーを利用して治療を行う方法です。整形外科でよく用いられる物理療法は、以下の通りです。● 温熱療法
● 水治療法
● 電気刺激療法
● 超音波
温熱療法(水治療法)では、ホットパックや温水を使用して患部を温めることで血行を促し、筋肉の緊張や痛みの緩和が期待できるでしょう。電気刺激療法には筋肉を刺激して筋力強化を図る「治療的電気刺激(TES)」、神経を刺激して痛みの軽減を図る「経皮的電気刺激(TENS)」などがあります。超音波も温熱療法と同じように、血行の促進や痛み・炎症の改善などを目的として行います。
動作指導
運動療法や物理療法以外にも、自宅での生活を安全に過ごすために動作指導を行うケースもあります。ケガによって身体機能が低下すると、日常生活にも支障が出る恐れがあります。身体機能の低下によってできなくなった、あるいはむずかしくなった動きを安全に行うために実施するのが指導です。
たとえば、足をケガしたことで普段行っていた床からの立ち上がりができなくなった方がいたとします。その方のために、足に負担のかからない新しい立ち方を教えたり、手すりの設置を勧めたりなどのアドバイスを行います。そのときの身体状況にあわせたカラダの使い方を学ぶのも、リハビリとして大切なポイントといえるでしょう。
整形外科のリハビリでかかる料金は?
ここでは整形外科のリハビリでかかる料金を説明します。リハビリの料金について、以下の表にまとめました。
| 単位数 | 1割負担 | 3割負担 |
| 運動器リハビリ(1単位) | 185円 | 555円 |
| 運動器リハビリ(2単位) | 370円 | 1110円 |
| 脳血管疾患等リハビリ(1単位) | 245円 | 735円 |
| 脳血管疾患等リハビリ(2単位) | 490円 | 1470円 |
リハビリは20分の時間を「1単位」として計算し、その単位ごとに料金が発生します。整形外科のリハビリでは、1〜2単位で行うことが多い傾向にあります。上記の表はあくまでも目安なので、クリニックや病院などによっては料金が異なる可能性があるので注意しましょう。
整形外科のリハビリに通うときのポイント
実際に整形外科でリハビリを続けていると、いつまで通えばいいのかの判断がむずかしくなることもあるでしょう。ただ、ずっと続けててもリハビリの効果がなかったら意味がありません。ここでは、リハビリを終了するタイミングを判断するポイントについて解説します。
ケガの具合によって通う頻度を調整する
ケガの治り具合によって、リハビリに通う頻度を調節してみましょう。ケガによって症状が強く現れている最初の時期では、週に2回以上のリハビリが望ましいです。その後、ケガが回復して症状が落ち着くようになったら、リハビリの頻度を少なくして変更して様子をみてみましょう。
このときに日常生活でも支障が出ないようであれば、リハビリの頻度を落としても問題ないといえるでしょう。リハビリに通う頻度をさらに落として、痛みが出なくなったり、再発のリスクがなくなったりしたら、やめても良いタイミングといえます。リハビリの頻度を一気に落とすとケガの回復具合が遅くなる可能性もあるので、少しずつ調整をしてみましょう。
自己判断でリハビリを中断しないようにする
自己判断でリハビリを中断しないように注意しましょう。リハビリを急に中止すると、症状の回復が遅れたり、身体機能の改善がうまくいかなかったりする恐れがあります。適切なリハビリ期間は一人ひとり異なるので、独断で判断せずに、医師とよく相談するようにしましょう。
あらかじめリハビリの目標を決めておく
リハビリ通いをスムーズに終了するためには、あらかじめ目標を決めておくことが大切です。「○○ができるようになる」「痛みが出ることなく日常生活を送れる」など、リハビリを行う目標を決めておきましょう。
具体的な内容を決めておくことで、リハビリの終了タイミングが明確となります。目標を決めずにリハビリを行っていると、そのまま意味なくズルズルと長引いてしまいます。担当の理学療法士や医師と相談しながら、なるべく早期の段階で自分の目標を作っておきましょう。
整形外科のリハビリ通いが終わったら?
リハビリ通いが終わっても、必要に応じて運動を継続する必要はあるでしょう。ここでは、整形外科でのリハビリ通いが終わった後の対応について解説します。
自宅でも行えるリハビリの準備をしておく
自宅でもリハビリを続けられるような準備をしておくことをおすすめします。リハビリ通いが終了しても、継続的な運動やケアは必要になる可能性は高いでしょう。とくにリハビリ期限が過ぎた後でも慢性的な痛みが続いたり、身体機能に支障が残ったりしている方は、引き続きリハビリが必要です。リハビリ通いが終わったときのために、あらかじめ理学療法士に自宅でのトレーニング内容についてアドバイスを聞いておきましょう。
自費リハの活用
整形外科の通いが終了した後も、質の高いリハビリを行いたい場合は、自費リハの活用も1つの手段です。自費リハとは、保険を使用せずに行うリハビリサービスのことです。保険適用外なので通常よりも料金はかかりますが、期間や回数などの制限がありません。そのため、自身が納得いくまでリハビリを続けられるのがメリットです。リハビリを継続してケガの具合や身体機能をより良くしたいと考えている方は、自費リハの活用も検討してみましょう。
介護保険サービスの活用
介護保険を持っている方であれば、介護保険サービスの活用もおすすめです。介護保険を適用したサービスにはさまざまな種類があり、リハビリに関係するのは「訪問リハビリ」や「通所リハビリ」などがあります。訪問リハビリは、スタッフが利用者の自宅に直接訪問してリハビリを提供するサービスです。通所リハビリ(デイケア)では、医療施設や老健などに通って食事やリハビリ、入浴などのサービスを受けられます。要支援や要介護を持っている方は、こちらの介護保険サービスをうまく利用してみましょう。
整形外科のリハビリにいつまで通うかをよく考えておこう(まとめ)
リハビリの通院は、その方のケガや身体機能の回復具合だけでなく、生活環境によっても大きく変わります。そのため、あらかじめリハビリのゴールを作っておき、定期的に医師や理学療法士と相談しながら進めることが大切です。また、なかには通院が終了した後もリハビリを続けたい方もいると思います。そのような方は、自主トレーニングメニューを作ったり、外部のリハビリサービスを利用したりなどの工夫をしてみましょう。
関連記事
関連ジャンル
最新コラム記事
-

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
-

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
-

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
-

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
-

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
-

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説
理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説