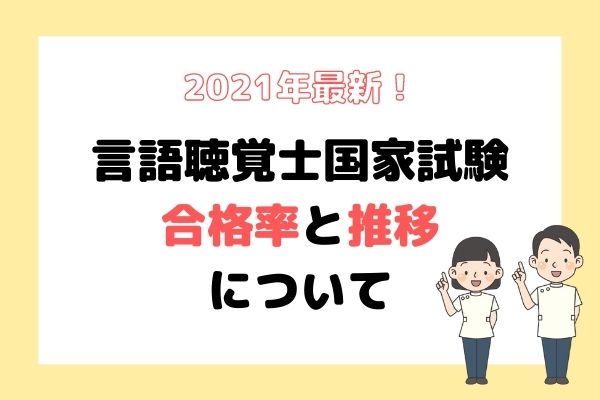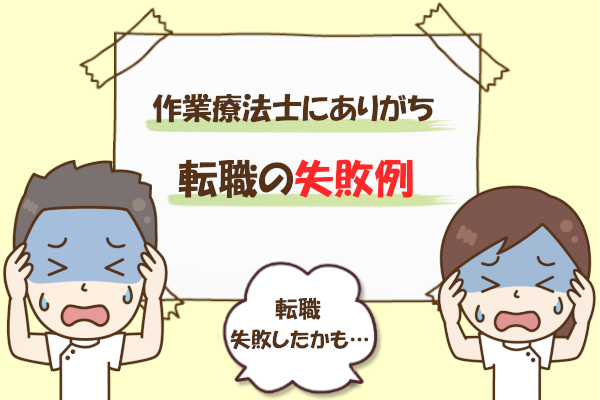言語聴覚士の業務は、失語症や高次脳機能障害、嚥下障害に対するリハビリが主になります。ただ、現代の日本では殆どが嚥下障害に対するリハビリが多くを占めています。
ですが、この嚥下障害はリスクが大きく、学校などでキチンとした訓練を受けれていないのが現実です。
その嚥下機能のリハビリに特化したかたちで始まったのが認定言語聴覚士です。
今回はこの認定言語聴覚士についてまとめました。
認定言語聴覚士とは
認定言語聴覚士は平成20年(2008年)に日本言語聴覚士協会によって作られた認定資格制度です。
上で書いたとおり、最初は嚥下障害に対する認定資格としてスタートしましたが、現在では、失語・高次脳機能障害領域、言語発達障害領域にも対応しています。 この資格が作られた経緯は、言語聴覚士の7割程度が関わっている嚥下障害に対し、キチンと教育を受けたものが、経験の浅い若い言語聴覚士である点。
また、40代以上の言語聴覚士ではそもそも学校などで学んでいない点。
このままでは満足した嚥下リハビリテーションを患者さんに提供できないことから、全国どこでも身近に嚥下リハビリテーションが受けられるようにという社会ニーズに合うようにとの思いから認定資格制度が作られました。
認定言語聴覚士が行う業務は、言語聴覚士とかわりません。
ただ、この資格をもった言語聴覚士は常に勉強し研鑽している証ですので、患者さんやご家族は安心してリハビリを受けていただけるでしょう。
認定言語聴覚士を取得するには
前提条件として、
- 言語聴覚士としての臨床経験が満5年以上ある
- 生涯学習システムの専門プログラム修了
- 関連科目言語・認知発達、言語・認知の加齢変化、音声言語聴覚医学、認知科学、心理学、言語学、音声学
- サービス提供システム
- 成人言語・認知失語、高次脳機能障害
- 言語発達障害
- 発声発語障害小児、成人
摂食嚥下障害 - 聴覚障害小児、成人
- 臨床実習
- 研究法
- 症例研究
資格を得ると認定言語聴覚士講習会を受けれるようになります。
この講習会(2日×3回)全てを同じ年度に受けることで、筆記試験が受けれます。
この筆記試験に合格することで、認定言語聴覚士になれます。
認定言語聴覚士は他の資格と同様に、5年毎の更新です。
更新要件は資格取得後5年以内に
- 学会に2回以上参加する
- 資格を取得した領域に関して、全国規模の学会で「発表」「講演」などから最低1つ行うこと
- 生涯学習プログラムの専門講座を受けて更に邁進すること
認定言語聴覚士を取得しても給与が増えることは、ほぼありません。
最新コラム記事
-

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
-

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
-

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
-

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
-

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
-

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説
理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説