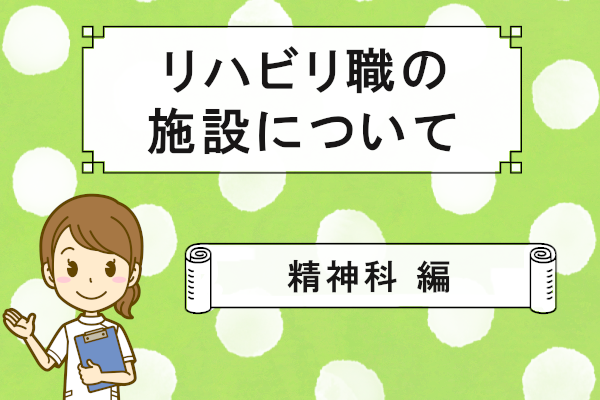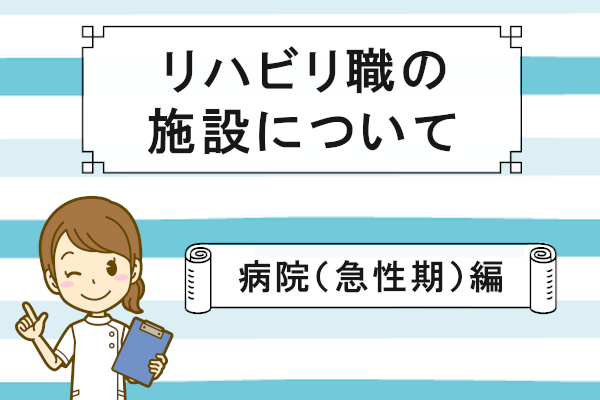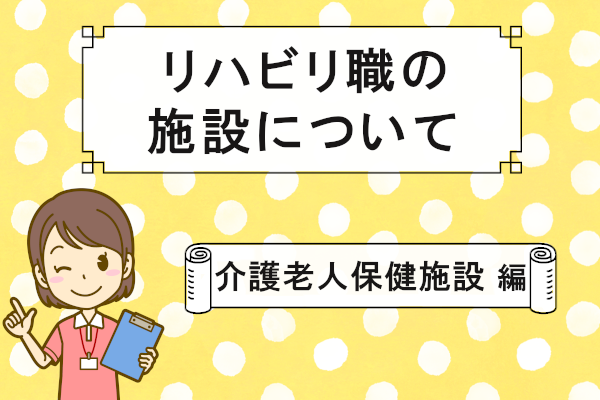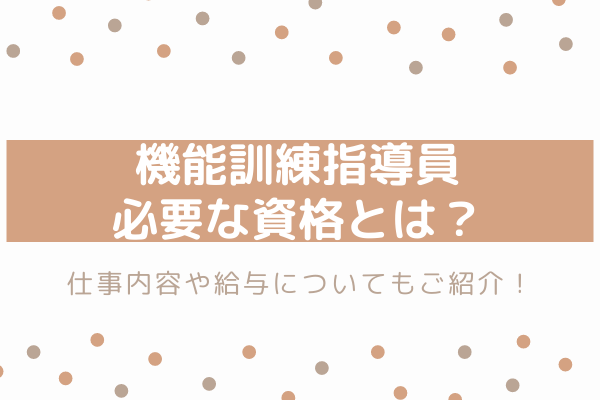病院(維持期)の施設形態について
病院の維持期リハに興味のある方に読んでほしい!維持期での仕事内容や診療報酬改定についてなどご紹介しています。
更新日:2020年01月08日
公開日:2020年01月07日
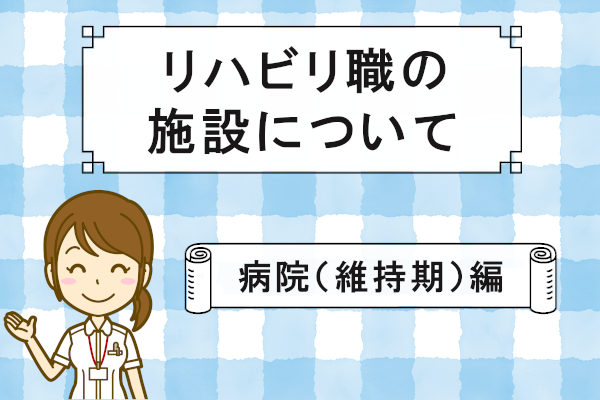
目次
維持期とは?
維持期とは生活期とも呼ばれる期間で、急性期や回復期で獲得した機能やADL(日常生活動作)能力などの「維持・向上」を目的としたリハビリをする時期です。維持期では、QOLつまり「人生の質・生活の質」の向上を目的にリハビリを行います。
維持期リハビリテーションの仕事内容について
病院で行う維持期リハビリテーションは、回復期までにやってきたリハビリを行いつつ、患者さんが実生活で役立つことを訓練し“出来ること”を増やしていきます。セラピストが行う維持期のリハビリは、QOLを向上させることが目的となっているため、各患者さんによってリハビリ内容は大きく異なります。
この時期に大切なことは、いま獲得している機能を維持させることやその人の生活によりそったケアを行うことです。
身体機能の回復よりも、動き方や日常生活の工夫、そして様々な作業を通して生活に楽しみを持ってもらうことが重要となります。
対象者の世代によっては、社会復帰をしてその人なりの自立した生活が送れるように、就労の支援を多職種の方と共にサポートしていくこともあります。
維持期リハビリテーションを受ける患者さんとは?
維持期リハビリテーションを必要とする患者さんは、入院中の方や退院し通院している方、若い方から高齢の方まで様々です。退院している患者さんは、週に何度かリハビリを受けるために通院します。
病状は安定しているけれど、リハビリに時間がかかり退院できない患者さんは、療養型病院(療養病棟)などに転院し継続してリハビリを受けます。
しかし、2019年4月に行われた「診療報酬改定」により、これまでのようにリハビリを受けられない方が続出しています。
病院で維持期リハビリテーションを受けられない?!~診療報酬改定について~
2019年4月より『要介護・要支援者への維持期・生活期リハビリの、医療保険給付から介護保険給付への移行』が完全実施となりました。※上記に該当する外来の維持期リハビリテーションは「脳血管疾患リハビリ」「廃用症候群リハビリ」「運動器リハビリ」です。
これまで、要介護・要支援認定を受けている高齢者で、退院後に通院し維持期のリハビリをしていた方は多くいます。
しかし、今回の診療報酬改定によって通院での維持期リハビリテーションが、医療保険給付から介護保険給付へ移行となったため、病院でリハビリを受けられる方が大幅に減少しました。
これによって、病院での維持期リハビリテーションが終了となってしまった患者さんは、介護施設への通所リハビリに切り替えなければなりません。
そのため、維持期のリハビリでは今まで以上にセラピストとケアマネージャーとの連携が必要となっています。
※参考:「厚生労働省|平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」
維持期リハビリテーションでの難しい点
維持期リハビリテーションをセラピストが行うなかで、難しいと感じる点は「リハビリの時間をしっかりと確保できないこと」「患者さんが良くなっている実感を得にくいこと」です。急性期や回復期では、入院しているためリハビリの時間をしっかりと確保できますが、維持期では退院し外来リハになるとリハビリ時間は入院時より短くなってしまいます。
また、維持期は回復期のように目に見える身体機能の回復が少ないため、患者さん自身が良くなっているという実感が得にくく、リハビリへのモチベーションが下がってしまいがちです。
維持期でのリハビリは“日々続ける”ことで身体機能の向上や回復に繋がります。
そのためには、患者さん自身が病院でのリハビリ以外に自宅でできる訓練を日々おこない、リハビリの時間を増やさなければなりません。
しかし、目に見える変化があまりない状況でリハビリを毎日続けることは簡単ではありません。患者さんに、少しでも「良くなっている」という実感を持ってもらえるように、心のケアをすることも大切です。
患者さんのリハビリへのモチベーションを上げることは、自宅でのリハビリに繋がり身体機能の向上や回復に影響するため、とても重要なケアの一つといえます。
「急性期や回復期も気になる!」という方はこちら↓を読んでみて下さい。
「病院(急性期)」の施設形態が気になる方!
「病院(回復期)」の施設形態が気になる方!
維持期リハビリテーションで働くには
維持期リハビリテーションで働くには、病院のホームページや求人情報からセラピストを募集している病院を探し、面接を受ける必要があります。しかし、数多くの求人情報から気になる病院を探し、どんな病院なのか一つひとつリサーチするのはとても大変ですよね。
求人情報やホームページだけでは分からないことも多いため、就職後に「思っていたのとちがった」と後悔する方は少なくありません。
できれば、事前にしっかりと職場の雰囲気や待遇面などを見て決めたいと思う方は多いはず。
そこで、おすすめなのが“転職エージェント”を利用する方法です。
転職エージェントは、人材紹介サービスの一つで転職のプロが就職先を探すサポートをしてくれます。
転職エージェントの一つであるPTOTSTワーカーでは、専任のキャリアアドバイザーが希望条件や悩みなどをしっかりとヒアリングし、あなたに合った求人を探し紹介してくれます。
事前に、職場の雰囲気を教えてもらえますし、見学の予約をしてもらうことも可能です。
入職までキャリアアドバイザーの手厚いサポートがあり、自分に合った職場を見つけられるため後悔のない就職ができます。
PTOTSTワーカーは、病院の求人が豊富!
まずは、求人情報を見て気になる病院を探してみてくださいね!
◎理学療法士の方はこちら
◎作業療法士の方はこちら
◎言語聴覚士の方はこちら
「他の施設も気になっている」という方はこちらから気になる施設を探してみて下さい!
最新コラム記事
-

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
-

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
-

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
-

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
-

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
-

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説
理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説