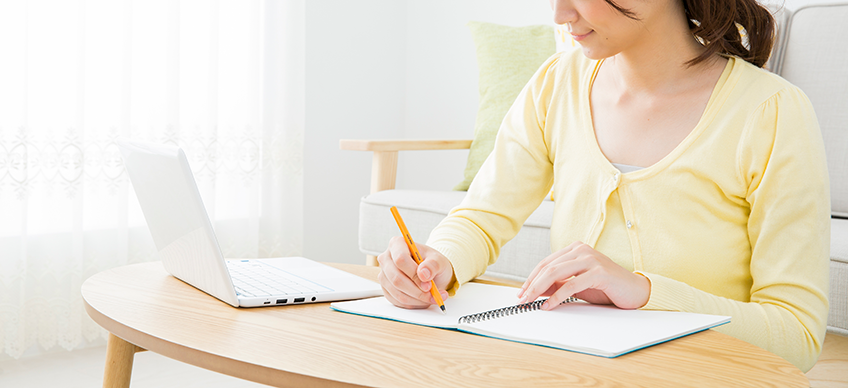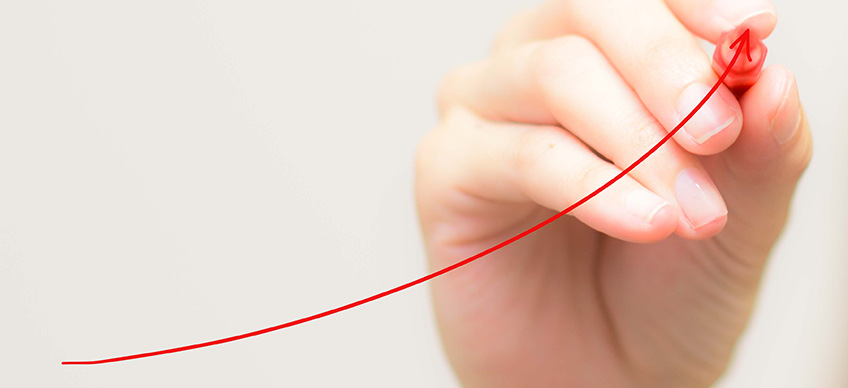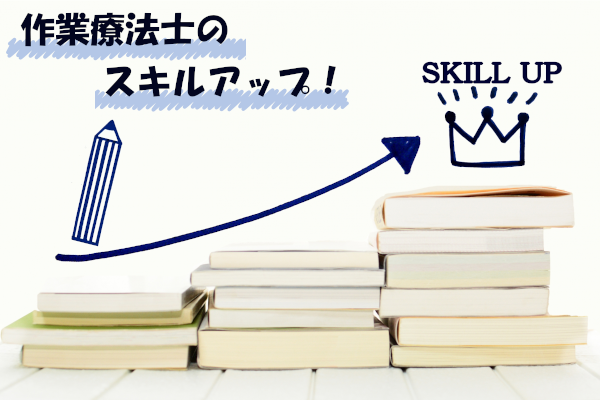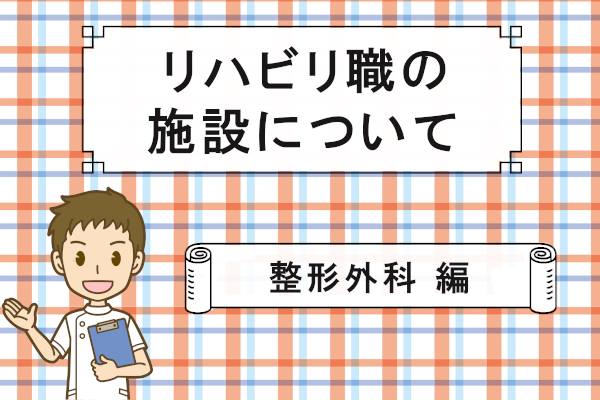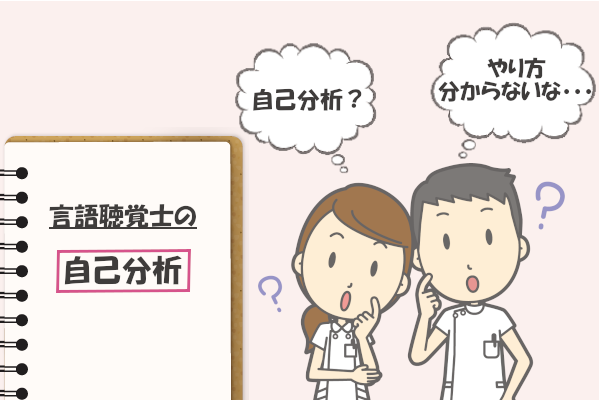脳の損傷などによって生じる構音障害。実際になってしまった場合は、できるだけ早く元の状態に回復していきたいかと思います。そのためには、症状や原因に合わせた適切なリハビリが大切です。
そこで、今回は構音障害のリハビリについて解説していきます。実際に自宅でもできるリハビリの方法もご紹介します。ぜひ、医療機関とも協力しながらリハビリを進めていってください。
目次
構音障害のリハビリとは?目的や効果は?
構音障害とは、他者の言葉は理解できるが、自分の言葉を発する際にろれつがまわらないことで、言葉が聞き取りにくい状態のことを指します。高齢の方も、子どもでもなる可能性はあります。ここでは、構音障害の概要について解説していきます。原因
構音障害とは、主に4つの種類に分けられます。それぞれの種類によって、原因となる疾病は変わってきます。主な原因は以下のとおりです。| 器質性構音障害…口腔がんの手術後、口蓋裂など 運動障害性構音障害…脳卒中、交通外傷による脳損傷。パーキンソン病や脳性麻痺など神経難病 聴覚性構音障害…難聴 機能性構音障害…原因不明 |
目的
構音障害のリハビリは、状態に応じてリハビリの目的は変わってきます。しかし、大切なことは本人の状態や意欲に合わせてリハビリの目的を変えていくことです。
例え軽度の構音障害であっても、本人の自責の念が強ければリハビリの重要度は高くなっていきます。そのため、本人の困難さを聞き取ったうえで、リハビリを考えていくようにしましょう。
効果
構音障害のリハビリの効果を上げていくには、医療機関の専門家の診断が必須です。構音障害と言っても、症状や状態は人によってさまざまです。
例えば、構音障害のみの診断であれば、後に紹介する言語訓練や構音訓練で口の筋肉をサポートしていくことがリハビリとして挙げられます。しかし、失語症などが絡んでいる場合は、違うアプローチをしなければいけません。
特に、構音障害と言っても原因や何が苦手かは人によってさまざまです。そのため、症状に合わせた適切なリハビリをすることで、リハビリの効果は高くなります。
構音障害に種類はある
原因でもご紹介しましたが、構音障害とは、主に4つの種類に分けられます。それぞれの種類によって、症状は変わってきます。主な症状は以下のとおりです。| 器質性構音障害…音がこもってしまう、特殊な発音 運動障害性構音障害…音がつながっているように聞こえる、話すリズムや速さが途中で乱れる 聴覚性構音障害…特定音に「ひずみ」が生じ聞き取りにくい 機能性構音障害…赤ちゃん言葉や他の音に置き換わる |
評価は必要?
リハビリの際に大切になってくるのが評価方法です。評価方法には、客観的評価と主観的評価があります。ここでは、病院やクリニックでも取り入れられてる評価方法について説明します。
評価方法には、2通りの方法があると言われています。
| 聴覚的評価…本人の言葉を聞き取っていく方法。聴き取る人によって、評価が割れてしまう場合がある。そのため、言語聴覚士などの専門家がおこなう。 機器的評価…超音波断層法、口腔・咽頭造影検査、ダイナミック・パラトグラムなど複数の機器を用いてどのように動くか評価していく。 |
病院や看護で実践されているリハビリの内容とは?
実際に構音障害のリハビリをしていく方は、どんな内容をしていくか不安があるかと思います。構音障害のリハビリは、状態や症状に合わせて2つのリハビリを中心におこなっていくことが多くなってきます。ここでは、2つの訓練についてご紹介します。
言語訓練
言語訓練とは、人が持っている「聞く、話す、読む、書く」の問題に対してアプローチしていくリハビリ方法です。構音障害は人によって、症状は違います。そのため、言語訓練とは、総合的にコミュニケーションに対して行っていくリハビリです。
例えば物の概念が思い出せない患者さんに対しては、絵カードやコミュニケーションカードを用いて物の理解を促していきます。このようにして、コミュニケーションを円滑になるようにするための訓練を言語訓練と言います。
構音訓練
構音訓練とは、脳損傷などにより構音器官(下あご、口、下、口蓋)に問題がある場合にしていく訓練です。先ほどの言語訓練と違い、表出する部分にのみ問題が生じている場合におこなわれている訓練です。
例えば、構音障害では口や下の動きが上手く動かせないことで発音にならない場合があります。その際に、口や下の教科を図るために舌体操をしていくことなどが挙げられます。
家でもできる!構音障害のリハビリの方法とは?
構音障害にはリハビリが大切です。一般的には、医療機関で専門家の指導の下リハビリを進めていきます。しかし、自宅でも時間がある際に「少しでも改善するようにしたい」という患者さんは多いかと思います。
そこで、自宅でもできるリハビリの方法を3つご紹介します。本人の意欲が大切になってくるので、無理がなく興味をもって出来そうなリハビリを選んでみてください。
パタカラ体操
家でも手軽にできる訓練として、「パタカラ体操」が挙げられます。パタカラ体操都は、口腔の機能を強化するために考えられた口の体操です。手軽に実施できるため、さまざまな場所で紹介されています。
やり方としては以下のとおりです。簡単です。「パ」「タ」「カ」「ラ」と、各10秒間できるだけ早く発音します。」発音のポイントは以下のところに気を付けてやってみてください。
「パ」唇をしっかり閉じる
「タ」上あごへ舌を打ちつける
「カ」のどの奥に力をいれる
「ラ」舌を上の前歯の裏につける
「引用:https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/897/engetaisou.pdf」
1人だと取り組みづらい方には、動画を見ながらやっていくとおすすめです。実際の口の動きも見られるため、口の動きがイメージしやすくなります。
「https://www.youtube.com/watch?v=3M6XOTQLlkg」
アプリ
家でもできるリハビリとして、アプリでのリハビリも注目されています。アプリを使うことで、普段と違ったリハビリができます。同じリハビリが続くと飽きが出てしまいますが、アプリにすることで患者の意欲の向上にもつながっていきます。ここでは、構音障害の肩に向けて使えるおすすめのアプリをご紹介します。
指電話は、有限会社オフィス結アジアで開発されたコニュケーションツールです。「かながわ産業Navi大賞2013 福祉支援賞受賞」も受賞した、専門家が開発したアプリです。
実際に登録した言語をAIが話してくれるため、失語症の方も使うことができます。有料版と無料版がありますので、使い勝手が良く気に入ったら、購入できるのも良いポイントとです。
https://www.yubidenwa.jp/
コミュニケーションカード
コミュニケーションカードとは、失語症の方などが絵や言葉が書かれたカートを渡すことで、コミュニケーションを円滑にしていく方法です。どの場所でも手軽に導入できやすいので、自宅でも手軽に始められます。
また、コミュニケーションカードをさらに進化したツールも販売されています。学校図書から販売されている「話したい、伝えたい!(発話支援のためのコミュニケーション・ツール)」は、トークンをタッチすることで音声が再生されます。日常生活の場面がより伝えやすくなっているので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
https://gakuto.co.jp/hanashitaitsutaetai/
自宅でのリハビリは無理なくやっていこう!
人にとって話が伝わらないということは、とてももどかしいことです。そのため、少しでも道具などを使って、伝わらない不満を減らしていくことが、構音障害のリハビリでは大切になってきます。
原因や症状も人によってさまざまです。だからこそ、医療機関やお医者さんと良く連携してリハビリを進めていくことが大切です。本人の意欲も大切にしながら、無理なくリハビリを進めていってみてください。
関連ジャンル
最新コラム記事
-

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
-

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
-

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
-

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
-

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
-

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説
理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説