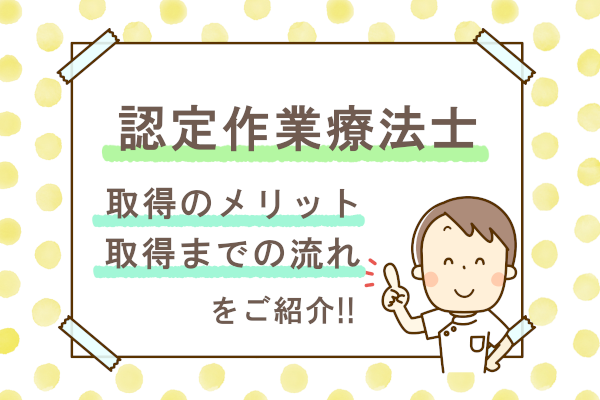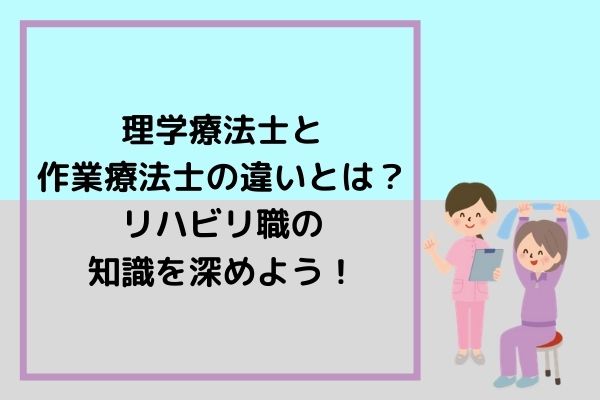脳梗塞になった後はどんなリハビリを行う?リハビリの効果や時期に応じた内容を解説
脳梗塞になった後はどんなリハビリを行う?リハビリの効果や時期に応じた内容を解説
更新日:2023年06月05日
公開日:2023年06月05日

自分の家族が急に脳梗塞になったとき、どのようなリハビリをするのか、どのくらい回復するのか心配になる方は多いのではないでしょうか。発症時期にあわせたリハビリの実施は、脳梗塞によって損傷した機能の改善につながります。この記事では、脳梗塞の方に行われるリハビリの効果や実施内容、家族ができるサポートの仕方などについてご紹介します。入院時のリハビリの流れについて理解しておけば、その後の退院までの段取りがスムーズになるでしょう。
目次
脳梗塞は脳卒中の1つ
脳梗塞とは「脳卒中」と呼ばれる疾患の1つであり、その他にも「脳出血」と「くも膜下出血」などがあります。 ここでは脳梗塞の概要について解説します。脳梗塞は脳の血管が詰まる病気
脳梗塞は血栓(血の塊)によって脳の血管が詰まって血流が障害される疾患です。血流が障害されて脳に栄養や酸素が届かなくなることで、さまざまな症状を引き起こします。脳梗塞はおもに以下の3種類に分かれます。● アテローム血栓性
● 心原性脳塞栓症
● ラクナ梗塞
アテローム血栓症とは、脳に続く血管に血栓やプラーク(脂肪の塊)が詰まることで引き起こされる脳梗塞です。心原性脳塞栓症は、心不全や心房細動などの心臓疾患によって引き起こされます。心臓内の血流の流れが乱れると血栓が生まれやすくなり、脳の血管を塞いでしまうリスクが高まります。ラクナ梗塞とは、脳内の小さな血管の詰まりによって引き起こされる種類の脳梗塞です。
脳梗塞のおもな原因は動脈硬化
脳梗塞を含めた脳卒中のおもな原因は動脈硬化です。 動脈硬化とは血管が硬くなって弾力性がなくなる疾患で、高血圧や加齢によって引き起こされます。動脈硬化になると血管内に血栓やプラークが生まれやすくなり、脳梗塞のリスクにつながります。その他の脳梗塞の原因となる要因は、以下の通りです。● 糖尿病
● 脂質異常症
● 不整脈
これらは生活習慣の乱れによって引き起こされる「生活習慣病」に含まれる疾患です。そのため、脳梗塞を予防するには生活習慣を整えることが欠かせません。上記の他にも、喫煙・飲酒も脳梗塞を引き起こしやすくなるため、禁煙やお酒の飲み過ぎを控えることが大切です。
脳梗塞による症状・後遺症
脳梗塞になるとどのような症状・後遺症が現れるのでしょうか。ここではおもな症状と後遺症についてご紹介します。片麻痺をはじめとした症状が現れる
脳梗塞になると以下のような症状が現れます。● 片麻痺
● 手足・顔面の痺れ
● 視界のぼやけ
● 声の出にくさ
● 嚥下障害(食べ物の飲み込みにくさ)
半身の手足が動きにくくなる「片麻痺」は、脳卒中の中でも代表的な症状といってもいいでしょう。片麻痺になるとうまく歩けずに転倒してしまったり、歯磨きや書字ができなかったりするため、日常生活に大きな支障が出る恐れがあります。
脳梗塞は飲み込みの障害も現れる可能性もあるので、食事の摂取が難しくなり誤嚥性肺炎につながることも。これらの症状は、脳の障害部位によって現れるものと現れないものがあります。
高次脳機能が障害されることも
脳梗塞は片麻痺や嚥下障害以外にも、「高次脳機能障害」が現れるのも特徴です。高次脳機能とは判断能力や認知能力など、人が持っている高度な知能のことで、その領域がダメージを受けると以下のような障害が現れます。● 記憶障害:新しいことが覚えられない
● 注意障害:注意が散漫となり、集中できない
● 遂行機能障害:計画を立てながら順序よく行動できない
● 社会的行動障害:感情がコントロールできず、社会性に欠如した行動をとってしまう
● 失語症:言葉が出にくくなったり、相手の話を理解できなかったりする
● 半側空間無視:見えている半分の空間に注意が向かなくなる
高次脳機能障害は身体的なものではなく、内面に現れる障害といえるでしょう。片麻痺や嚥下障害などを含めた症状は後遺症として残る可能性があるため、治療後もうまく付き合っていく必要があります。
脳梗塞の発症後にリハビリをする重要性
脳梗塞の発症後は、なるべく早めのリハビリを行うことが重要です。「脳卒中ガイドライン」によると、脳卒中が発症したら早期にリハビリを行うことがすすめられています。 脳卒中になった後に寝たきり状態だと筋肉や骨が衰えて、身体機能が低下する恐れがあります。脳は障害された機能を回復するために、残った神経がダメージを受けた部分を補うように適応するのをご存じでしょうか。 この神経の働きはリハビリによって活性化されやすくなりますが、3〜6か月ほどで落ち着きます。 そのため、早期のリハビリは機能の改善が期待できるのです。
実際に、早期から積極的なリハビリテーションと退院支援を行うことで、入院日数が短縮したという報告があります。さらにADL(日常生活の動作)やQOL(生活の質)の向上も認められているため、 いかに早期のリハビリが大切かがわかるでしょう。
出典:Ⅶ.リハビリテーション - 日本神経治療学会
脳梗塞のリハビリ期間
脳梗塞のリハビリ期間はその人の症状によっても異なるため、決まりはありません。しかし、脳梗塞の再発予防や身体機能の維持をするためにも、継続的なリハビリは重要といえるでしょう。ここで注意したいのは、病院には期限がある点です。脳梗塞のリハビリによって入院できる期間は、高次脳機能障害がともなっている場合で最大で180日です。 これは現在の医療保険の制度によって決められており、一部例外もありますが基本的にその期日が入院の最大日数です。退院後もリハビリを効率的に続けるためには、通所リハビリや訪問看護サービスなどを受けることがおすすめです。
脳梗塞になった後のリハビリの流れ
脳梗塞になった後は、発症時期にあわせたリハビリを行うことが基本です。おもにリハビリは以下の3つの時期に分かれます。● 急性期でのリハビリ
● 回復期でのリハビリ
● 生活期でのリハビリ
ここではそれぞれの時期にあわせたリハビリの流れについてご紹介します。
急性期でのリハビリ
急性期は脳梗塞を発症した直後の時期です。身体の状態が急変しやすい時期なので、積極的な運動よりも寝たきりによる身体機能の低下を防ぐことを目的にハビリを行います。おもなリハビリ内容は以下の通りです。● 手足の関節を動かす運動
● 片麻痺となった手足のポジショニン
● ベッド上での寝返り
● ベッドからの起き上がり
● ベッドから車イスへの乗り移り
基本的にベッドサイドでのリハビリが多いですが、状態にあわせて立ったり歩いたりなどの運動も行います。また、発症から48時間までのリハビリでは、歩行をはじめとした機能の改善が期待できるといわれています。
回復期でのリハビリ
急性期が経過し、徐々に脳梗塞の症状が落ち着く時期が回復期です。この時期では症状の安定化にともなって積極的なリハビリが行えるため、身体機能を改善する重要な期間といえるでしょう。回復期で行うリハビリ内容は以下の通りです。● 積極的な離床
● 立ったり歩いたりする運動
● 装具を使用した運動
● 日常動作で使用する動きの練習
● 応用的な動きの練習
● 高次脳機能を改善するためのリハビリ
● 飲み込みの練習
このように、回復期のリハビリのバリエーションは急性期と比較すると非常に多くなります。回復期の後半では退院に向けて、自宅に戻って実際の動作をしたり、泊まったりなどをして安全に過ごせるかを確認します。
生活期でのリハビリ
回復期を過ぎて、身体機能の改善も落ち着く時期が生活期(慢性期)です。この時期になると病院を退院した方が多いので、自宅で過ごしていても身体機能を維持・改善できるようにリハビリを行います。生活期でリハビリを受けられるサービスは、おもに以下の通りです。● 通所リハビリ
● 訪問リハビリ
● デイサービス(リハビリ特化型)
● 自費リハビリ
身体機能を衰えさせないためにも、上記のサービスを利用して継続的にリハビリを受けることが大切です。サービスの利用だけでなく、自宅での自主トレーニングも並行しておくといいでしょう。
脳梗塞のリハビリ内容
病院で行う脳梗塞のリハビリは、おもに以下の3つに分類されます。● 理学療法
● 作業療法
● 言語療法
ここではそれぞれのリハビリ内容についてご紹介します。
歩いたり立ったりなどを行う理学療法
理学療法では立つ、座る、歩くなどの日常生活で用いられる基本的な動きの改善を目指します。具体的なリハビリ内容としては以下の通りです。● 起居動作練習
● 歩行練習
● 筋力トレーニング
● ストレッチ
● 日常生活動作の練習
片麻痺の影響で筋力が大きく低下している場合は、装具を活用することもあるでしょう。リハビリの際は「理学療法士」と呼ばれる専門職が症状や動きを評価しつつ、その方にあわせた内容を提供するのが特徴です。
応用動作のリハビリを行う作業療法
基本的な動きだけでなく、応用的な動きに関するサポートを中心に行うのが作業療法です。作業療法では、おもに手を使用したリハビリを「作業療法士」とともに行います。リハビリ内容の例としては、以下の通りです。● 服を着る練習
● 編み物の練習
● パソコンのタイピング
このように、日常生活で必要な動きから仕事や趣味に使う動きなど、その方にマッチしたリハビリを行います。人によっては食材を使用して料理をしたり、掃除や洗濯などの家事を真似たりなどを実践することもあります。
理学療法が「足のリハビリ」だとしたら、作業療法は「手のリハビリ」というイメージだとわかりやすいでしょう。しかし、どちらも手・足だけのリハビリを行うわけではありません。作業療法でも、状況に応じて足を中心にリハビリを行うケースもあります。
声や食事のリハビリを行う言語療法
言語療法では、嚥下障害や高次脳機能障害などの改善のために以下のようなリハビリを行います。● 声を出す練習
● 食べ物をうまく飲み込むための練習
● 記憶力を定着させるための練習
● 注意を向けるための練習
飲み込みの練習では食事の形態を変えたり、飲み物にとろみをつけたりなど、その方の嚥下機能に応じた工夫も欠かせません。高次脳機能障害の場合も、その種類にあわせた課題を行って症状の改善を目指します。言語療法は「言語聴覚士」と呼ばれるリハビリ職によって実施されます。
理学療法と作業療法が手足・身体に対してのリハビリだとしたら、言語聴覚は頭や顔の機能を改善するためのものといえるでしょう。このように、リハビリは3つの内容に分かれており、症状にあわせてそれぞれの専門職がサポートをします。
脳梗塞の方のご家族によるサポートについて
家族が脳梗塞となってしまった場合、どのようなことをしてあげられるでしょうか。ここでは、家族ができるサポートについてご紹介します。リハビリに参加する
可能であればリハビリ現場を見学したり、一緒に運動に参加したりしてあげましょう。家族がリハビリに参加すれば入院している方のモチベーションも上がり、身体機能の改善につながります。実際に家族がそばに居てくれると、リハビリを積極的に行ってくれる方は多くみられます。スタッフとしても家族が参加してくれるのはありがたいので、ぜひ時間があるときにリハビリ現場の見学をしてみてください。メンタルのサポート
家族のサポートは入院している方のメンタルケアにつながります。脳梗塞は急に起こる病気なので、いきなり身体が動かなくなってショックを受けたり、鬱傾向になったりする方も珍しくありません。発症して最初の時期は精神面が不安定となる可能性は高いので、定期的な面会でメンタルのケアをしてあげることはとても大切です。入院している方も「回復できるように頑張りたい」「リハビリで病気を治したい」という気持ちが高まるので、スタッフとともにサポートをしてあげましょう。退院に向けての準備を進めておく
リハビリを進めて少しずつ退院が見えてきた場合は、自宅へ帰るための準備を進めておきましょう。介護保険が取得できるなら申請を進めたり、ケアマネと相談して自宅改修をしたりすることが大切です。場合によっては、歩行や車イスの乗り移りなどの介助が必要になる可能性もあります。介助をスムーズに行うためには、入院中にリハビリスタッフに相談をしてどのように行えばいいかの指導を受けることも大切です。脳梗塞の方がリハビリを行う必要性をおさえておこう(まとめ)
脳梗塞を発症すると片麻痺や高次脳機能障害など、さまざまな障害が現れます。それらの症状の改善を目指すには、発症後の早期のタイミングでリハビリをすることが大切です。入院中はリハビリ見学をしたり、面会で会話をしたりなど、家族にできるサポートもたくさんあるでしょう。ぜひ院内のスタッフと協力しながら、脳梗塞になった方の支援をしてみましょう。関連ジャンル
最新コラム記事
-

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
-

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
-

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
-

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
-

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
-

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説
理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説