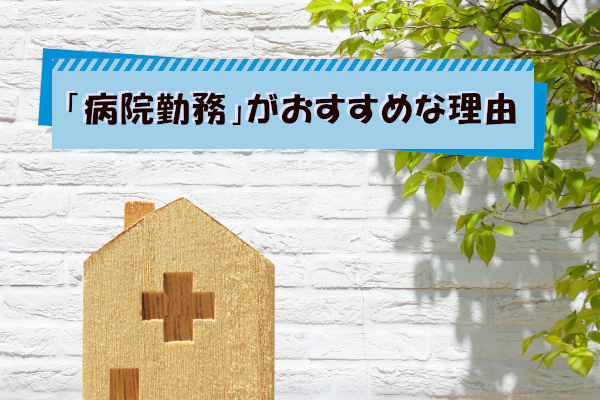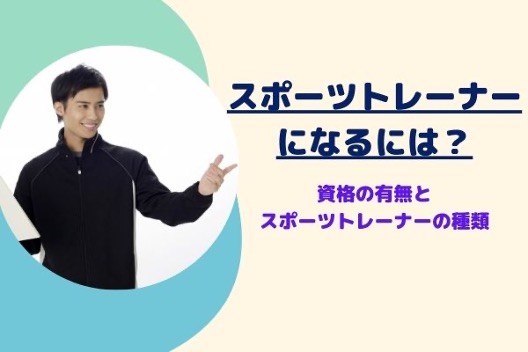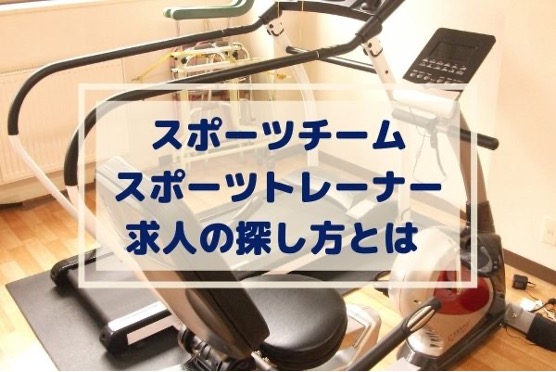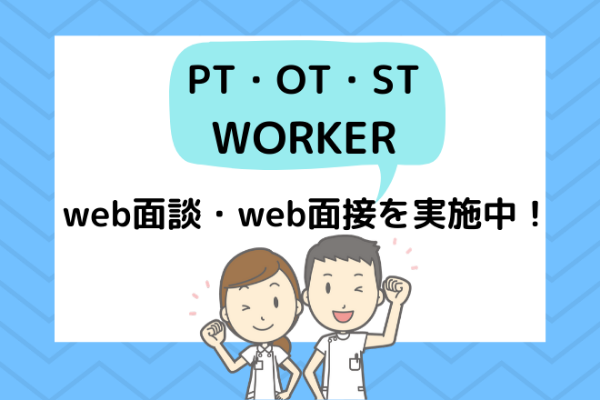理学療法士がスポーツ分野で活躍するには?仕事内容や就業先、求人の探し方などを解説!
スポーツ分野で活躍する理学療法士の仕事内容や就職先、求人の探し方など詳しく解説しています!
更新日:2023年04月06日
公開日:2021年06月21日

理学療法士として働ける場所は医療機関だけでなく、高齢者の自立支援や社会復帰の支援の場となる介護・福祉分野のほか、プロスポーツチームのトレーナーとしてなど、スポーツ分野にも広がりをみせています。
最近では、リハビリテーション医療における理学療法の知識をスポーツの分野でも活かせるカリキュラムを取り入れる養成学校も増えており、ますますその活動領域は広がる一方となっています。
そのため、理学療法士を志す方のなかには、資格を活かしてスポーツ分野で活躍したいと考える方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、リハビリの専門職である理学療法士がスポーツ分野で活躍するために知っておきたい、仕事内容や就職先、またスポーツトレーナーになるための方法や求人の探し方など、さまざまな疑問について詳しく解説していきます。
スポーツ分野における理学療法士の仕事内容とは
一般的な理学療法士の仕事内容は、病気や怪我、高齢によって運動機能が低下した人を対象に、理学療法を用いて身体機能の改善・維持を図るためのリハビリを行うことですが、スポーツ分野においてはどのような仕事内容が挙げられるのでしょうか。スポーツのプロチームで活躍する理学療法士の働き方と、フィットネスなどで活躍する理学療法士の働き方について確認していきましょう。
スポーツのプロチームにおける理学療法士の働き方
理学療法士がスポーツ選手と関わる場面は怪我のリハビリのイメージが強いかもしれませんが、それだけではありません。スポーツのプロチームに専属として就く理学療法士は、突然の怪我や病気に対する応急処置といった救急対応をはじめ、リハビリの指導や競技に合わせた体の使い方、怪我をしない体づくりや能力向上のためのトレーニング指導など、幅広い業務を通して選手の総合ケアを担います。
たとえば、野球選手に関わる理学療法士では、ケガをしない投球フォームへと改善するための体の使い方の指導を行います。
ですが、テニス・野球・サッカー・バレーボールなど、競技によって使う筋肉や疲労が蓄積しやすい部位は当然ながら異なります。
そのため、スポーツのプロチームに所属する理学療法士は、それぞれの競技に対する専門的なスポーツ知識と医学的な知識によるケアがより大切なものとなります。
とはいえ、スポーツ選手と怪我は切っても切り離せないものです。
普段から体のケアをきちんと行い、怪我をしない体づくりを行っていたとしても、接触などのアクシデントというのは起こりえます。
選手が怪我をしてしまった際には、理学療法士はその選手を心身両面から支えることが必要になってきます。
リハビリを行っていても思うようにいかなかった場合、選手にフラストレーションがたまり思いがけない言葉をかけられることもあるかもしれません。
それでもその心理状態を理解し、寄り添い、支えると言った姿勢で目の前の選手と向き合うこともまた、理学療法士がスポーツのプロチームで担う重要な役割のひとつです。
フィットネスなどにおける理学療法士の働き方
スポーツ分野で働く理学療法士は、プロのスポーツチームに所属することだけが活躍の場ではありません。フィットネス施設や地域スポーツ、障がい者スポーツなどにおけるサポートやトレーナーとしての活動もまた、理学療法士として働ける場所のひとつです。
所属する施設や関わるスポーツによって働き方はそれぞれですが、いずれも理学療法士としての医学的知見をもとに、筋肉や関節の動きなどを理解したうえでスポーツに関わる人をサポートするといった点では共通した役割が多くみられます。
たとえば、フィットネス施設では医学的な知見から生活習慣病などに考慮した個別の運動プログラムをもとにトレーニング指導を行ったり、筋肉や関節の動きから身体状態を評価したうえで医学的根拠のあるトレーニング方法をアドバイスしたりすることが主な仕事となります。
また、地域スポーツにおいては高校サッカーや野球といった部活動、またアマチュアスポーツに所属する選手に対し、正しいトレーニング方法を指導したり怪我をしないための体つくりをサポートしたりすることが主な役割です。
障がい者スポーツも地域スポーツ同様、理学療法士として身につけている障害への知識をもとに、怪我の予防や痛みの緩和のためのリハビリやケアを通し、選手やチーム全体をサポートすることが理学療法士の重要な役割となります。
特に、障がい者スポーツでは車いすや義足などを使用されることも多くあります。
障がい者スポーツに関わる理学療法士は、義足の調整や車いすのシーティングの調整を通して、選手やチームのパフォーマンス向上のための支援を行うシーンも多々みられます。
スポーツトレーナーになるには?資格の有無とスポーツトレーナーの種類
スポーツと関わりのある仕事に就きたい理学療法士にとって、スポーツトレーナーは人気の職種です。スポーツトレーナーとは、スポーツ選手が最大限のパフォーマンスができるように、怪我の予防やリハビリ、トレーニング指導などを行う役割の総称をいいますが、ケアの対象となる人はスポーツ選手に限らずアマチュア選手から一般の方までさまざまです。
また、スポーツトレーナーといって職種はひとつではなく、得意とする役割ごとにトレーナーの名称は異なり、それぞれがもつ専門性や仕事内容には違いがあります。
以下では、スポーツトレーナーのなるために資格の有無について、またスポーツトレーナーの種類についてご紹介しています。
理学療法士の資格を活かしてスポーツトレーナーになりたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
スポーツトレーナーになるための必須資格はない
スポーツ選手を支えるスポーツトレーナーは、いわば縁の下の力持ち。スポーツトレーナーになるためには、何かしらの資格が必要と考える方も多いでしょう。
しかし実は、スポーツトレーナーのなるための必須資格はありません。
もちろん、国家資格である理学療法士のように持っていると有利といわれる資格はいくつかありますが、無資格でもスポーツトレーナーとして活躍している方は多くいます。
ただし、狭き門であるプロのスポーツチームに専属で就くということを目指すのであれば、海外でも通用するスポーツトレーナー関連の認定資格や医療の専門資格を取得する必要はあるでしょう。
スポーツトレーナーの種類
スポーツトレーナーはプロのアスリート選手だけでなく、アマチュアのスポーツチームから部活動、一般の方までさまざまなシーンでスポーツと関わりを持ち、指導やサポートを行っています。スポーツトレーナーの種類は役割ごとに分けると5種類ありますが、重なる業務内容もあることから複数のトレーナー業務を兼務している人も少なくありません。
■アスレティックトレーナー
アスレティックトレーナーは、スポーツ現場における怪我の応急措置や救命措置、また怪我・障害の予防を専門とするトレーナーです。
日々の健康管理はもちろん、怪我から復帰するためのリハビリを通したサポートのほか、テーピングやアイシング、止血といった応急措置から人工呼吸や心臓マッサージなどの救命措置に関する専門知識が求められます。
スポーツトレーナーのなかでは最も認知度が高く、アスレティックトレーナーが担う業務には医療にかかわる部分も多くあるため「メディカルスタッフ」や「メディカルスタッフ」と呼ばれることもあります。
■メディカルトレーナー
メディカルトレーナーとは、スポーツ選手の怪我の治療やリハビリをはじめ、試合に向けた日々のコンディション調整を専門とするトレーナーで、怪我からの復帰に向けたメンタルケアなども担います。
メディカルトレーナーはスポーツ選手だけでなく、一般の方や高齢者の運動機能回復を目的としたリハビリや体力回復のための指導、介護予防のトレーニング指導なども行います。
メディカルトレーナーになるには医学的知識と技術が求められるため、多くはスポーツ系の大学・短大・専門学校に通いメディカルトレーナーの民間資格を取得している、あるいは理学療法士などの医療系資格の取得しているケースが一般的です。
■コンディショニングトレーナー
コンディショニングトレーナーは、主にスポーツ選手の健康管理(体調管理)と、怪我をしない体づくりとして独自のトレーニングメニューの考案や指導などを専門としたトレーナーです。
怪我の応急処置などを行うアスレティックトレーナーや怪我の回復やリハビリを担うメディカルトレーナーと比べ、コンディショニングトレーナーは練習など日常における怪我の予防といった選手のコンディショニングに重点をおいた指導が中心となります。
なお、スポーツ選手の怪我予防と最大限のパフォーマンスを引き出すためのコンディショニングに重きをおいている点では、「フィジカルトレーナー」もコンディショニングトレーナーと同じ役割を担っています。
フィジカルトレーナーは理学療法士や柔道整復師といった医療系の国家資格を持つ人が多く、プロのスポーツチームや選手に帯同することも多くあります。
■ストレングストレーナー
ストレングストレーナーは、プロのアスリート選手をはじめスポーツ選手の肉体づくりを専門としたトレーナーです。
スポーツにおけるパフォーマンスの向上を目的とし、筋力アップやパワー・持久力の向上、怪我をしない体づくりなどを中心としたトレーニング指導を行うため、スポーツ競技において欠かせない存在です。
具体的なサポート内容は、サポート対象者の身体機能や体力アップを目標としたトレーニングメニューを作成しトレーニングの指導を行うことで、スポーツにおけるパフォーマンスの向上を目的としています。
■フィットネストレーナー
フィットネストレーナーは、主にフィットネスクラブやスポーツジムにおいてトレーニング指導などのサポートを専門とするトレーナーで、マンツーマンで指導を行うこともあるため「パーソナルトレーナー」と呼ばれることもあります。
フィットネストレーナーとしてトレーニング指導を行うには、骨格や筋肉、関節などの人体への深い知識をはじめ、食事や栄養に関する知識、スポーツやトレーニングに関する知識が求められます。
★こちらの記事もおすすめ!
理学療法士がフリーランスとして活躍するなら知っておきたい「メリット・デメリット」
スポーツ分野で活躍する理学療法士の就業先例
スポーツ分野で活躍する理学療法士の就業先には、スポーツチーム(プロ・アマチュア)をはじめ、企業やスポーツジム、フィットネスクラブ、強豪チームとして有名な部活動をもつ高校や大学、地域のスポーツクラブなどが挙げられます。また、スポーツが原因で怪我をした方のリハビリを力を入れている整形外科やスポーツ整体院なども、スポーツ分野で活躍する理学療法士の就業先の例として挙げられます。
理学療法士がスポーツ分野で有利になれる資格
理学療法士がスポーツ分野で活躍するために有利とされる資格には、「CSS(認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト)」や「日本スポーツリハビリテーション学会認定トレーナー」といった民間資格のほか、国家資格である柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師、アスレティックトレーナーなどのダブルライセンスが挙げられます。こちらでは、民間資格である「CSCS」と「日本スポーツリハビリテーション学会認定トレーナー」について、どのような資格なのかご紹介していきます。
CSCS(認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト)
「CSCS(認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト)」とは、スポーツにおける怪我や傷害の予防とスポーツパフォーマンス向上を目的とした、安全で効果的なトレーニングプログラムを計画・実行する知識と技能を有する人材を認定する資格です。この資格は特定非営利活動法人NSCAジャパン(日本ストレングス&コンディショニング協会)が主催する民間資格で、1985年に認定試験が開始されて以降、スポーツトレーナーとして活躍する人をはじめ医師や研究者なども資格を取得しています。
「CSCS(認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト)」は、ストレングス&コンディショニングの認定資格として唯一全米資格認定委員会(NCCA)の承認を受けており、国内だけでなく海外でも通用する資格として知られています。
認定試験では、解剖生理学やトレーニングの基礎知識をはじめ、実践的なシチュエーションに対する解答などが求められ、2019年度の認定試験の合格率は47.7%と難易度は高め。
受験者向けの必須講習などはないため、試験に挑む各々が自身に合った学習計画を立てて受験対策をする必要があります。
「CSCS(認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト)」公式サイト
日本スポーツリハビリテーション学会認定トレーナー
「日本スポーツリハビリテーション学会認定トレーナー」とは、スポーツ障害を含む運動器疾患の発生あるいは疾患の再発予防における知識のもと指導できる人材、また支援を行える人材を認定するための認定制度で、日本スポーツリハビリテーション学会が主催しています。この認定制度では、健康科学的側面から怪我の予防や疾患の再発防止を目的とし、適切なトレーニングやコンディショニング指導を行える専門技術者の養成と認定を行っています。
2019年時点における日本スポーツリハビリテーション学会認定トレーナーの名簿に記載されているトレーナー数は168名で、大半のトレーナーが柔道整復師の資格を保有するほか、医学療法士、アスレティックトレーナー、医師、学生などが認定されています。
日本スポーツリハビリテーション学会認定トレーナーになるには、まず本学会の会員であることを必須とし、最低60時間のセミナーの受講ののち認定試験(筆記試験100問)を受ける必要があります。
認定試験では、解剖学や運動学、スポーツ傷害や応急措置についてなど幅広い内容を勉強する必要があるため、苦手分野の克服やセミナー受講における計画的なスケジュール調整などが重要です。
「日本スポーツリハビリテーション学会認定トレーナー」公式サイト
スポーツ分野に強い理学療法士の養成学校・大学はどこ?
スポーツ分野に強みをもつ理学療法士の養成学校は以前よりも増えており、専門学校や大学などさまざまな学校でスポーツとリハビリに関する知識と技術を身につけることができます。こちらではたくさんある養成学校のなかから、特に「スポーツ×リハビリ」の特色が大きな大学と専門学校を抜粋してご紹介します。
■大阪保健医療大学
大阪保健医療大学は、医療・介護・福祉・スポーツなど、さまざまな領域における現代のニーズに対応できるセラピストの育成に注力している大学です。
病院や小児施設や研究機関、訪問リハなどさまざまな臨床経験をしてきたプロとなる教員による授業が充実しており、スポーツ分野においては障害者スポーツを通して学びを深めるプロジェクトや、スポーツの臨床現場の見学などが実習以外の学びの場として設けられています。
国家資格の取得だけでなく、初級・中級障がい者スポーツ指導員など目指したい分野で活かせる関連資格の取得サポートも行われています。
■新潟医療福祉大学
新潟医療福祉大学は、看護、リハビリ、医療、栄養、スポーツ、福祉、医療事務・医療情報分野の総合大学で、各学科の専門性を活かしスポーツリハビリを実践的に学べることが強みです。
充実した設備環境と理学療法士の活躍領域に応じた学びで、医療や介護、福祉だけでなくあらゆるニーズに対応できる理学療法士の育成に力を入れています。
■履正社医療スポーツ専門学校
履正社医療スポーツ専門学校は「スポーツの履正社」とも呼ばれ、スポーツトレーナーや理学療法士、柔道整復師などの資格取得が目指せる専門学校で、関西では唯一となる理学療法士と日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーの資格が同時に取得できる専門学校でもあります。
独自に設けられた「ダブルラーニング制度」では、競技・トレーナー・医療・英語の4つの領域を自由に組み合わせて履修することができ、より専門性の高い人材の育成に注力しています。
ダブルラーニング制度では、特定の競技を専門的に学びながら医療を学ぶ「メディカルアスリート専攻」、特定の競技に特化したアスレティックトレーナーの育成を目的とした「競技&アスレティックトレーナー」、医療系国家資格を活かしトレーナーとして現場で即戦力となれる「医療+アスレティックトレーナー」のほか、スポーツ・医療の現場で活かせる英語力を身につけるコースが用意されています。
■名古屋医健スポーツ専門学校
名古屋医健スポーツ専門学校は、スポーツ・保育・医療・リハビリ・福祉に強い専門学校です。
こちらの専門学校では、スポーツ現場で活かせるトレーナーとしての知識と技術の習得を目的に、「スポーツ現場力アカデミー(NISA)」を開講しています。
「スポーツ現場力アカデミー(NISA)」では、テーピングやストレッチといった基礎をはじめ、解剖学や生理学、スポーツ傷害などの知識習得、スポーツ現場での実践的対処といった専門的な学びによりスポーツ現場力のある理学療法士の育成に力を入れています。
■島根リハビリテーション学院
島根リハビリテーション学院では、医療現場や福祉・介護の現場におけるリハビリ知識だけでなく、近隣の高校運動部でトレーナー活動を実施するなど、スポーツ現場で活かせる理学療法を実践的に学べます。
また2020年度からは新たに自由選択科目が設置され、アスレティックトレーナーなど将来の進路を見据えたカリキュラム制度が導入されています。
スポーツ現場で活躍するうえで必要な怪我の予防やスポーツ傷害、コンディショニングなどの知識のほか、高校やプロスポーツへの帯同も経験できる点は大きな魅力といえます。
★こちらの記事もおすすめ!
理学療法士に必要な知識とは?養成学校での勉強内容を徹底解説!
競技以外の生涯スポーツでは作業療法士の活躍も
スポーツと関わるリハビリ職と聞くと理学療法士が頭に浮かぶ方が多いと思いますが、実は作業療法士もスポーツと関わる機会はあります。とはいっても、スポーツ選手や地域のスポーツチームなどでサポートにあたる理学療法士のような仕事ではなく、作業療法士がスポーツと関わるのは作業療法のなかで取り入れるレクリエーション運動です。
作業療法士が治療・支援の一環として行うレクリエーション運動では、日常のなかで簡単にできるスポーツをリハビリのひとつとして取り入れています。
その例として実際に作業療法の場で行われているレクリエーション運動には、風船をボールに見立て参加者同士でパスを行う「風船バレー」というものがあります。
室内で気軽にできること、また通常のボールよりも落下速度がゆるやかであることから、高齢者から精神疾患のある方まで抵抗なく参加できるレクリエーションとなっています。
このように、競技スポーツとの関わりが深い理学療法士とは異なり、作業療法士はスポーツを治療のひとつとして、レクリエーションを通して生涯スポーツと関わっています。
スポーツチームの求人、スポーツトレーナーの求人の探し方
日本には、野球やサッカーといったメジャースポーツをはじめ、ラグビーやアイスホッケー、アメリカンフットボール、バスケットボール、ハンドボールなどさまざまな競技におけるプロのスポーツチームがあります。しかし、プロのスポーツチームに専属の理学療法士として就職する人はごく一握りです。
そのため、理学療法士としてスポーツチームに就職をして食べていくというのは、なかなか厳しい現実かもしれません。
というのも、スポーツ分野で活躍したいと考えるトレーナーや理学療法士などはごまんといるからです。
競争が常に高い分野において圧倒的につかみ取れるポジションが少ないことで、どうしても経験を通して積み上げてきた実績や取得資格などでライバルとの差が大きく開くということも少なくありません。
とはいえ、全くチャンスがないというわけでもありません。
たとえば、1年目に病院に就職し週末にジュニアのスポーツチームにスポーツトレーナーとして関わるなど、そのなかから繋がりができることで将来的にプロチームに関わることだって不可能ではありません。
基本的に、プロのスポーツチームに帯同するトレーナーや理学療法士などの募集は公にはされておらず、ほとんどは人からの紹介やコネクションが中心の世界ですから、活躍したい競技に関連する場所や施設などで地道に経験を積むことでチャンスをつかみ取れる可能性はあります。
一方、プロのスポーツチーム以外で活躍するスポーツトレーナーの道は比較的就職先が見つかりやすい傾向にあります。
スポーツトレーナーの求人はさまざまな媒体で掲載されており、就職先はスポーツクラブやフィットネスジム、スポーツクリニックや整骨院、介護施設、病院併設のトレーニング施設などがあります。
スポーツ整形の実績が高いクリニックでは医師がスポーツチームのドクターとして活躍していることも多く、理学療法士としてチームに同行しトレーナー業務を経験できるケースもあります。
希少なスポーツトレーナーの求人においては、転職エージェントを通して紹介してもらうこともおすすめです。
理学療法士や作業療法士などリハビリ職に特化した転職エージェントであるPTOTSTワーカーでは、気象なスポーツトレーナーの求人を取り扱っています。
気になる方はぜひPTOTSTワーカーでチェックしてみてください。
■【完全無料!】PTOTSTワーカーへの登録はこちらから♪
スポーツ領域の理学療法士はフィジオと呼ばれている
理学療法士は英語でPhysiotherapist(フィジオセラピスト)といいます。
理学療法士はスポーツ領域ではフィジオと呼ばれているようです。
難しく考える必要はなく看護師をナースと呼ぶのと同じような感じです。
そのほかにもフィジカルコーチやアスレチックトレーナーなどと呼ばれるものもありますが、2つできる方もいらっしゃればこれらすべてをフィジオが担うチームもあるようです。
フィジオはあらゆる判断を一瞬で行わなければなりませんし、応急処置や予防など幅広く知識を持っている必要があります。
学校を卒業し理学療法士の国家試験に合格したとしてもすぐにスポーツチームに関わるのは少し危険が伴います。
なぜならスポーツの世界はシビアだからです。この人はダメだ!と思われたらもうそのフィジオには近づきません。
スポーツ選手が結果を求められるようにフィジオにとっても早い段階で結果を求められます。
良くも悪くも結果がすべての世界ですので、「スポーツに関わりたい!」と思っていても慌てることなく、スポーツチームのフィジオとして活躍できるように経験を積むことが大切です。
★こちらの記事もおすすめ!
認定理学療法士を取得する3つのメリットとは!?
最新コラム記事
-

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
-

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
-

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
-

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
-

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
-

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説
理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説