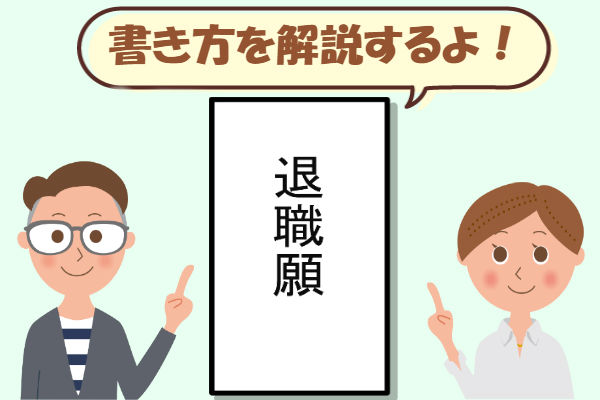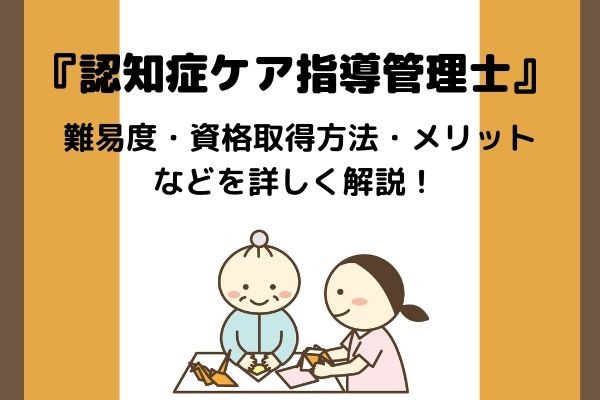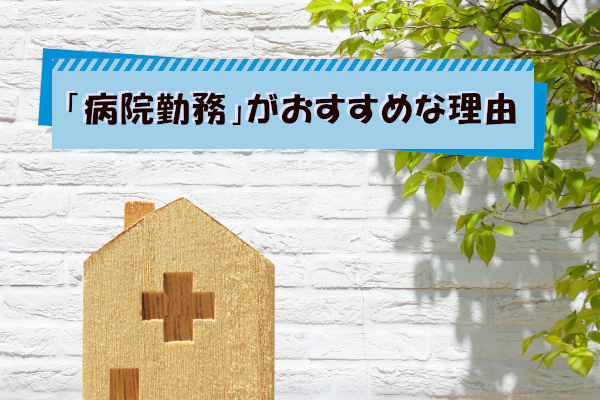478呼吸法にはどんな効果がある?やり方や注意点についてご紹介
478呼吸法にはどんな効果がある?やり方や注意点についてご紹介
更新日:2023年02月16日
公開日:2023年02月16日

「478呼吸法」はリラックスしたり、寝つきがよくなったりする効果があるといわれています。しかし本当に効果があるのか、どのように行えばいいのかなどを知りたい人も多いのではないでしょうか。この記事では、478呼吸法のやり方や効果、実施する際の注意点をご紹介します。478呼吸法の特徴をおさえつつ、適切な方法で学んで普段の生活に役立ててみましょう。
目次
478呼吸法とは?
478呼吸法とは、アメリカの「アンドルー・ワイル教授」という方が提唱した方法で、別名「マインドフルネス呼吸法」ともいわれています。 もともとヨガの瞑想で用いられていた呼吸法が原点で、その方法を応用したといわれています。
478呼吸法には寝つきがよくなる、リラックス効果があるとされており、それを検証するために過去に研究も行われました。その結果、被験者の睡眠の質が高まったと報告されています。このように、478呼吸法は臨床的にも心が落ち着く効果があるとされています。
478呼吸法の効果
478呼吸法はなぜ効果があるのでしょうか。ここでは478呼吸法の代表的な効果と、その仕組みを詳しく説明します。リラックス効果
478呼吸法にリラックス効果がある理由として、腹式呼吸によって自律神経が整えられる点です。腹式呼吸を行うと、リラックスするための「副交感神経」が優位に切り替わります。実際に、緊張したときやイライラしたときに深呼吸をすると、心が冷静になるような体験をした人はいるのではないでしょうか。
それは腹式呼吸によって、活動するための「交感神経」の働きが弱まり「副交感神経」が優位になっているからです。寝つきが悪い人は、寝ているときも交感神経が優位になっている可能性があります。478呼吸法を行って副交感神経に切り替えることで、寝つきの悪さが解消され、良質な睡眠につながります。
血流の促進
478呼吸法は血流を促進させる働きもあります。腹式呼吸を行うと、肺の下にあるドーム上の筋肉の「横隔膜」が収縮・弛緩を繰り返します。この横隔膜の運動によって周囲の内臓が適度に圧迫され、血流の促進につながるのです。
血液の循環がよくなれば、足のむくみが改善したり、腸の働きが活発となり便秘が解消されたりする効果が期待できます。478呼吸法は寝つきが悪い人だけでなく、冷え性や便秘に困っている人にも活用できます。
姿勢崩れの防止
478呼吸法を行うと、姿勢崩れの改善や肩こり・腰痛予防につながります。これは478呼吸法で横隔膜の運動が活発になると、周囲の体幹筋も活動しやすくなるからです。腹筋や背筋などの体幹筋は、キレイな姿勢を保ったり身体を動かすときにバランスをとったりする働きがあります。
この体幹筋が衰えると、姿勢が崩れて肩こり・腰痛の原因になるだけでなく、身体バランスも悪くなるのです。運動不足の人、あるいはデスクワークで肩こり・腰痛に悩んでいる人は、ぜひ478呼吸法を行ってみましょう。仕事の合間の短い時間でも、気軽に姿勢のケアを行えますよ。
478呼吸法のやり方
ここでは478呼吸法のやり方についてみていきましょう。
【478呼吸法のやり方】
1.あお向けの姿勢、またはイスに座った姿勢でリラックスする
2.口から息を最後まで吐ききる
3.息を最後まで吐ききったら、4つ数えながら鼻から息を静かに吸う
4.息を止めて7つ数える
5.8つ数えながら、口からゆっくり息を吐ききる
6.再び3〜5の流れを繰り返す
この「吸う・止める・吐く」のリズムが「4・7・8」なので、478呼吸法といわれています。4・7・8のカウントは「秒」ではなく、自分にあった快適なリズムでかまいません。吐くときに大きく口を開けると息が続かなくなるので、なるべく口をすぼめた状態で行いましょう。478呼吸法を何回もたくさん行って息が苦しくならないように、4サイクル程度を目安にして行ってみましょう。
487呼吸法を行う際の注意点
478呼吸法は、実施する回数やタイミングによっては効果を実感しないこともあります。ここでは478呼吸法を行う際の注意点について説明します。やりすぎには注意
478呼吸法は行えば行うほど効果が現れるわけではなく、逆にやりすぎると気分が悪くなることもあります。とくに腹式呼吸をうまくできずに478呼吸法をすると、十分な空気の換気ができずに過呼吸を引き起こす危険性があります。はじめのうちは、1日4回程度を目安にして行うことをおすすめします。
腹式呼吸をうまく行っているかを確認するためには、お腹と肋骨の下部に手を当ててみましょう。腹式呼吸によって横隔膜が働いていれば、息を吸うときに手を当てた部分が広がります。過呼吸だけでなく、めまいや動悸などがみられたら、すぐに中止しましょう。
日中に頻繁に行うと眠れなくなる可能性がある
日中に478呼吸法を頻繁に行うと、夜に眠れなくなる可能性があります。日中の人の身体は基本的に交感神経が優位となっており、夜になると自然と副交感神経に切り替わります。しかし日中に478呼吸法を頻繁に行い、中途半端に副交感神経に切り替えてしまうと、自律神経のリズムが崩れやすくなるのです。
その結果、夜になっても副交感神経に切り替わらず、かえって眠れなくなる危険性があります。もちろん日中に478呼吸を行うだけで、すぐに自律神経が乱れるわけではありませんが、このような懸念がある点は覚えておきましょう。478呼吸を行うタイミングは、副交感神経に切り替わる夜中や寝る前がおすすめです。
478呼吸法の効果を高めるコツ
478呼吸法だけでも十分にリラックスできますが、工夫次第でさらに効果を高めることが可能です。ここでは478呼吸法の効果を高めるためのコツについてご紹介します。リラックスできるアロマを使用する
アロマを使用しながら478呼吸法を行うと、さらなるリラックス効果が期待できます。好きな香りを楽しむアロマセラピーには、以下のような効果があるとされています。
● リラックス効果
● 睡眠の質の向上
● 血行促進
● ホルモンバランスの改善 など
このように、メンタル面だけでなく身体のケアにもつながるため、478呼吸との相性は良好です。香りのもととなる精油にもさまざまな種類があるので、自分が心地いいと感じる香りを選択してみましょう。
睡眠前の明かりを暗くする
寝る前に478呼吸法を行うとき、部屋の明かりを暗くしておけば眠りにつきやすくなります。夕方以降になると、少しずつ「メラトニン」と呼ばれる睡眠ホルモンが分泌され、眠気が強くなります。このメラトニンの分泌に重要なのが、周りの明るさです。
メラトニンは周りが暗くなるほど分泌されやすいため、夜は照明の光を控えめにしておくと眠りにつきやすくなります。478呼吸法の事前準備として、夜になったら照明の明るさをおさえて、睡眠ホルモンの分泌を促しておきましょう。
ストレッチを行う
筋肉のストレッチをしておくこともおすすめです。ストレッチにより筋肉をゆるめることで、血流の促進やリラックス効果が得られます。副交感神経も優位となりやすいので、質の高い睡眠につながります。
ストレッチ中に息を止めたり、痛みが強くなるまで筋肉を伸ばしたりすると、逆に交感神経が優位になる危険性があるので注意しましょう。呼吸を整えつつ、心地よい範囲で筋肉を伸ばすことを心がけましょう。ストレッチで筋肉をゆるめた状態で478呼吸法を行えば、リラックス効果がさらに高まるでしょう。
478呼吸法はこんな人におすすめ
478呼吸法はリラックス効果だけでなく、その他にもさまざまなメリットがあります。ここでは478呼吸法をおすすめしたい人についてご紹介します。ストレスがたまっている人
478呼吸法は、ストレスがたまっている人におすすめです。日々の仕事が忙しかったり、人間関係がうまくいかなかったりすると、ストレスや不安が蓄積するものです。その状態が続くと交感神経が常に優位になり、副交感神経に切り替わりにくくなります。
リラックスできる状態をなかなか作れなくなるので、ストレスや不安を助長してしまうことも。478呼吸法ではストレスや不安を軽減させる効果があるので、心を休める手段として取り入れてみましょう。
寝つきが悪い人
478呼吸法の効果にも説明したとおり、寝つきが悪い人にもおすすめです。これはストレスがたまっている人にも関連しますが、寝つきが悪い人は副交感神経の切り替えがうまくできていない可能性があります。そのため、寝る前に478呼吸法で心を落ち着かせて、身体がリラックスできる状態を作りましょう。血圧が高い人
478呼吸は自律神経が原因で血圧が高い人にも効果が期待できます。交感神経は活動するための神経のため、血圧を上昇させる働きがあります。しかしストレスや寝不足などによって交感神経がずっと優位になっていると、血圧は高いままです。
この状態が続くと、高血圧や脳卒中などの病気につながる危険性もあるでしょう。478呼吸を行って副交感神経を優位にすることで、リラックス効果により血圧が低下します。ストレスや寝不足が原因で血圧を上げないためにも、478呼吸で心身をリラックスする時間を設けましょう。
腰痛や肩こりがある人
478呼吸法は、腰痛や肩こりの解消にも役立ちます。腹式呼吸による横隔膜の運動で周囲の体幹筋が刺激されるので、キレイな姿勢の保持につながります。腰痛や肩こりは姿勢の悪さから生じることが多いので、キレイな姿勢をキープすれば自然と解消されることもあるでしょう。
「最近、腰痛や肩こりが気になる…」と感じている人は、試しに478呼吸を行ってみるのもいいかもしれません。同時に姿勢そのものを意識したり、トレーニングで体幹筋を鍛えたりすれば、さらなる腰痛・肩こり予防になります。
478呼吸法以外の方法
478呼吸法以外にも、さまざまな呼吸法があるのはご存じでしょうか。ここでは、別の呼吸法についてご紹介します。腹式呼吸法
腹式呼吸を活用した方法です。腹式呼吸はヨガの基本的な呼吸法だといわれており、気分をリラックスさせて交感神経から副交感神経に切り替えます。腹式呼吸法のやり方は以下のとおりです。
【腹式呼吸法のやり方】
1.あお向けの姿勢、またはイスに座った姿勢でリラックスする
2.自然な呼吸を意識する
3.お腹をへこませながら、鼻からゆっくりと息を吐ききる
4.鼻からゆっくりと息を吸って、お腹を膨らませる
5.再び3と4を繰り返す
このときにお腹を意識して、しっかりとへこんでいるか、膨らんでいるかを確認しましょう。
丹田呼吸法
丹田呼吸法は、おへその下にある「丹田」と呼ばれる部分を意識して行う方法です。丹田呼吸法のやり方は以下のとおりです。
【丹田呼吸法のやり方】
1.リラックスした姿勢で、おへその下(丹田)に手を置く
2.自然な呼吸を意識する
3.丹田をへこませるように、鼻からゆっくりと息を吐ききる
4.鼻からゆっくりと息を吸って、丹田を膨らませる
5.再び3と4を繰り返す
このように、腹式呼吸とやり方は似ていますが、こちらの方法は丹田を意識します。最初は丹田を意識するのがむずかしいと思いますが、少しずつ呼吸を繰り返すとリラックスした状態を作れます。
代替鼻孔呼吸法
代替鼻孔呼吸法とは、左右の鼻から交互に呼吸をする方法です。この方法もヨガの呼吸法であり、深いリラックス効果を促します。代替鼻孔呼吸法は以下の流れで行います。
【代替鼻孔呼吸法のやり方】
1.リラックスした姿勢で自然な呼吸を意識する
2.手で右側の鼻を塞いで、左側から息を深く吸う
3.左側の鼻を塞いで、右側から息をゆっくりと吐く
4.左側の鼻を塞いで、右側から息を深く吸う
5.右側の鼻を塞いで、左側から息をゆっくりと吐く
6.再び2から5を繰り返す
代替鼻孔呼吸法は左右の鼻で呼吸するので、風邪や花粉症で鼻がつまっていたら、別の呼吸法を実施しましょう。
深呼吸をカウントする方法
最後に、深呼吸をカウントする方法も心を落ち着かせるには有効です。深呼吸をカウントする方法は以下の流れで行います。
【深呼吸をカウントするやり方】
1.リラックスした姿勢で自然な呼吸を意識する
2.深く息を吸う
3.深く息を吐いて1つ数える
4.再び2と3を繰り返し、5まで数えたらまた1から数え直す
深呼吸をカウントする方法は、他の呼吸法と比べるとシンプルなのが特徴です。
このように、478呼吸法以外にもさまざまな呼吸法がありますが、どれも共通してリラックス効果がある点です。もし「478呼吸法ではイマイチ効果がない…」と感じる人がいれば、ぜひ別の呼吸法にもチャレンジしてみましょう。
適切な方法で478呼吸法を行ってみよう
478呼吸法には心を落ち着かせるだけでなく、血液の循環をよくしたり姿勢を整えたりする効果もあります。そのため、夜に寝付けない人や腰痛・肩こりに悩んでいる人におすすめの呼吸法です。やり方もシンプルなので、興味がある人はぜひ今日から478呼吸法を試してみてください。その他の呼吸法もご紹介しているので、自分にピッタリな方法を見つけて心をリフレッシュしましょう。関連ジャンル
最新コラム記事
-

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
-

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
-

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
-

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
-

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
-

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説
理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説