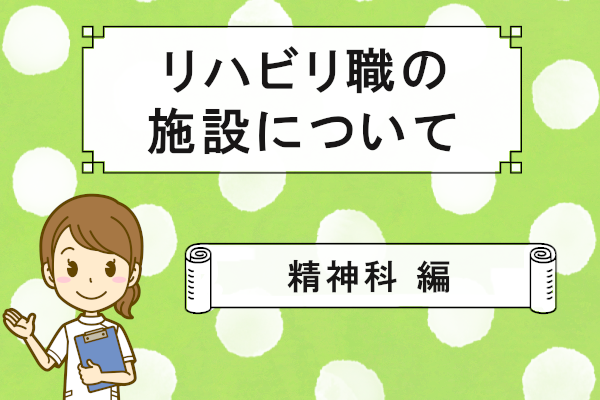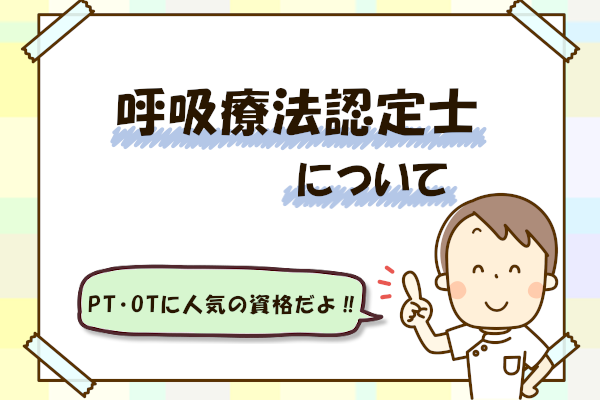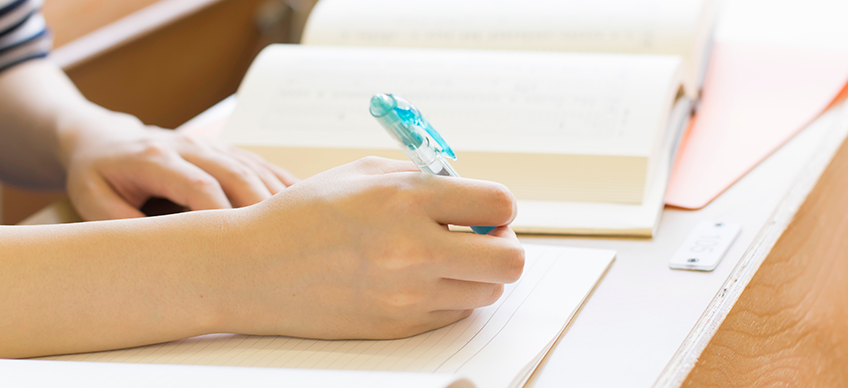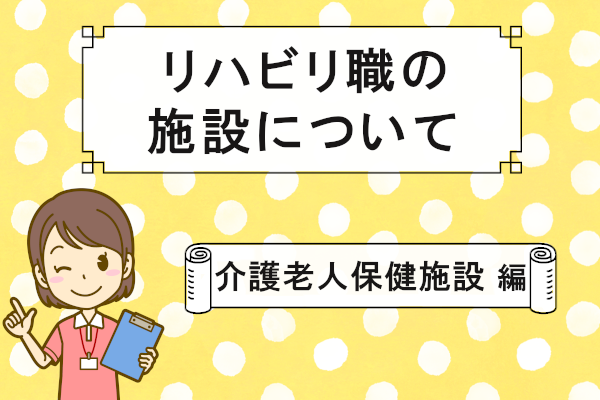呼吸器疾患は、病院を退院後も継続的なリハビリを行う必要がありますが、どのような運動を行えばいいかわからない方もいると思います。呼吸リハビリでは有酸素運動や筋力トレーニングが効果的とされており、事前に身体のコンディショニングを行うことも重要です。この記事では、呼吸リハビリの効果や内容についてご紹介します。呼吸リハビリについておさえておけば、自宅でもムリのない運動を継続でき、症状の改善が期待できるでしょう。
目次
呼吸リハビリテーションとは
呼吸リハビリとはどのような治療なのでしょうか。ここでは呼吸リハビリを行う目的や必要性について解説します。呼吸リハビリテーションの目的
呼吸リハビリとは、呼吸器疾患を抱えた方が安全に日常生活を送るための治療法です。 具体的な目的として、以下の3つがあげられます。
1.呼吸機能の障害による、活動時の呼吸困難をやわらげること
2.呼吸困難による日常生活の動作の不自由を改善すること
3.気道感染をはじめとした症状悪化の原因を予防すること
呼吸器疾患を完全に治療するのはむずかしいでしょう。しかし、上記の目的でリハビリを行うことで、呼吸が楽になり、QOL(生活の質)の向上が期待できるのです。
呼吸リハビリテーションの必要性
呼吸リハビリは活動性を高めて、呼吸機能の維持・向上を図るために必要な取り組みです。慢性的な呼吸器疾患があると、次第に呼吸機能が低下し、息切れを起こす頻度が多くなります。息切れが起こりやすいと活動の機会が減り、体力や筋力の低下につながります。結果的に「体力・筋力が低下→活動しなくなる→さらに呼吸機能が落ちる」のような悪循環に陥ってしまうのです。
この悪循環を止めるためには、呼吸リハビリを行って呼吸機能の低下を防ぐことが大切です。とくに退院後はリハビリを受ける機会が少なくなるので、自主的に取り組んでいく必要があるでしょう。
呼吸リハビリテーションの対象疾患
どのような疾患の方が呼吸リハビリを行うべきなのでしょうか。ここでは呼吸リハビリの対象となる代表的な疾患をご紹介します。COPD
COPD(Chronic Obstructive Pulmonary Disease)とは「慢性閉塞性肺疾患」ともいわれている肺の病気です。以前は「肺気腫」と「慢性気管支炎」に分けられていましたが、現在ではこの2つの病気をあわせてCOPDと呼ぶようになりました。気管支の炎症、肺胞の損傷などによって肺の機能が低下し、咳や息切れ、呼吸困難などの症状が現れます。COPD の最大の原因は喫煙によるものですが、その他にも遺伝や大気汚染によって発症するケースもあります。
気管支喘息
気管支喘息は、気管の慢性的な炎症によって起こる疾患です。なんらかの刺激によって気管が細くなることで、以下の症状が発作的に現れます。
● 呼吸困難
● 咳
● 喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューなどの呼吸)
これらの症状は夜から朝にかけての時間帯に起こりやすく、日中は比較的落ち着いているのが特徴です。気管支喘息の原因はアレルギー反応によるものが多く、ダニはハウスダストなどに反応して発症します。
気管支拡張症
気管支拡張症とは、気管支が広がって元に戻らなくなる疾患です。気管支が広がることで細菌を排除する機能が低下し、痰や咳が出やすくなります。その他にも咳や痰に血が混じる喀血(かっけつ)や血痰(けったん)が生じる恐れもあります。
気管支拡張症の原因は、先天性と後天性のものがあります。後天的なものとしては、気管支の感染や炎症の繰り返しによって起こる他、別の疾患がきっかけで発症するケースもあります。
間質性肺炎
間質性肺炎とは、肺にある「肺胞」と呼ばれる器官が炎症や損傷を起こして、繊維化する疾患です。肺胞とは小さな袋のようなもので、酸素を取り込んでガス交換を行う役割があります。繊維化によって肺胞が硬くなると、ガス交換がスムーズにできなくなり、活動時に息切れを起こしやすくなります。
その他にも、痰が出ない咳の「乾性咳嗽(かんせいがいそう)」という症状が現れるのも特徴です。間質性肺炎の原因は以下の通りです。
● 関節リウマチや強皮症などの自己免疫疾患によるもの
● ほこりやカビなどによる刺激
● 薬物・サプリメントなどによるアレルギー反応
なかには原因が特定できないものもあり、それを「特発性間質性肺炎」と呼びます。特発性間質性肺炎にもいくつかの種類に分かれており、現在は難病指定を受けています。
呼吸リハビリテーションの効果
呼吸リハビリには吸困難や体力低下の改善が期待されており、健康状態・QOLの向上につながるとされています。この効果は薬物療法による治療と並行して行うことで、さらなる改善が見込めるとされています。 実際に、COPDを抱えた患者さんに運動療法と薬物療法を組み合わせた結果、以下の結果が得られました。
● 動いたときの呼吸困難の軽減
● 活動性の向上
● QOLの改善[2]
また世界各国の診療ガイドラインでは、呼吸リハビリが強く推奨されています。退院後の維持期だけでなく、発症後の急性期、回復期でも、呼吸リハビリのエビデンスは多く集まっています。
このように、呼吸器疾患の症状を改善するには、呼吸リハビリがいかに重要であるかがわかるでしょう。
出典:呼吸リハビリテーションに関するステートメント
1 Ⅰ.推奨グレードの決定およびエビデンスレベルの分類
呼吸リハビリテーションの評価
呼吸リハビリでは、呼吸状態をはじめとした身体状況をさまざまな方法で評価する必要があります。おもに歩行や入浴、階段を歩いたときの身体の変化を指標とします。たとえば、歩行では一定の時間歩いたときの心拍数や歩行距離、息苦しさを測定するケースが多いでしょう。入浴では服を脱いでお風呂に浸かってから、身体を洗った後にタオルで拭くまでで、どの動きが疲れやすいのかをチェックします。
これらは呼吸リハビリ前後で、どのような改善がみられたのかを測る指標でもあります。医療機関では細かな評価を行えますが、在宅ではなかなか身体状況を調べるのはむずかしいでしょう。そのため「呼吸リハビリをしてから疲れにくくなった」「息切れが減った」など、自覚症状の変化を感じることが大切です。
呼吸リハビリテーションの内容
呼吸リハビリにはさまざまな種類があります。ここではおもに行われる呼吸リハビリについてご紹介します。運動療法
運動療法は運動を中心とした治療法で、呼吸リハビリのなかでも重要な役割を持っています。ここでは運動療法で行われる内容をみていきましょう。
コンディショニング
コンディショニングでは、本格的な運動療法を行う前の準備として行われます。比較的負荷の低い運動で呼吸や身体の状態を調整し、その後の運動療法の効果を高める役割があります。具体的な内容は以下の通りです。
● 呼吸練習
● 胸郭の可動域練習
● 体幹のストレッチ
● 排痰運動
慢性的な呼吸器疾患を抱えている方は、呼吸に関係する胸郭を中心とした全身の柔軟性や筋力が低下しています。その状態で運動を行っても高い効果が得られにくいため、コンディショニングによって受難性を引き出し、筋肉が活動できるように整えます。
有酸素運動
有酸素運動は低負荷で行われる全身持久力とレーニングであり、呼吸困難の軽減や体力向上の効果が期待されています。激しい運動を行うのではなく「ややきつい」程度の負荷量にとどめて長時間行うのが特徴です。有酸素運動の代表的な内容は以下の通りです。
● ウォーキング
● サイクリング
● エルゴメーター
● 水中歩行
● ノルディックウォーキング
これらの運動は負荷量を自由に調節できるので、呼吸器疾患を抱えている方でも行いやすいといえるでしょう。
筋力トレーニング
筋力(レジスタンス)トレーニングでは、筋肉量の増加を目的として行われます。運動内容の例は以下の通りです。
【足の運動】
● スクワット
● かかと上げ
● 座った状態で膝伸ばし
【腕の運動】
● 両手を上に伸ばす
● 壁を使って立った状態で腕立て伏せ
【体幹の運動】
● 寝た状態で頭上げ
● 腹筋
● 寝た状態で足上げ
有酸素運動だけでは筋肉量の増加は期待できないので、併用して行うことのがおすすめです。有酸素運動と筋力トレーニングの組み合わせにより、呼吸困難の症状のさらなる軽減が期待されています。
栄養療法
呼吸リハビリは運動だけではなく、栄養管理も同じように重要です。栄養療法では、食事の栄養バランスを整えて体重や筋肉量の減少を予防します。栄養障害になると、肺機能や呼吸筋の低下を引き起こし、呼吸困難の頻度を高めたり、QOLが低下したりするリスクが高まります。
また栄養が不十分の状態で運動療法を行っても、エネルギーの消費量がさらに増えるので高い効果は得られにくいでしょう。早期の段階で栄養バランスを整え、運動機能の維持、全身状態の改善に努めることが大切です。
薬物療法
運動療法や栄養療法の他にも、薬物療法によって症状の悪化をおさえることも重要です。使用する薬は疾患によってさまざまです。たとえば、COPDを抱えている方には吸入薬を中心に使用します。吸入薬には気管支を広げる薬や、気管支・肺の炎症をおさえる薬などの種類があります。
薬を服用するタイミングや回数などはあらかじめ決められており、誤った飲み方をしてしまうと、思うような効果は得られません。必ず医師の指導のもと、正しい方法で薬物療法を行いましょう。
これらの呼吸リハビリの他にも、酸素療法や教育指導などを行うケースもあります。
呼吸リハビリテーションを行う際の注意点
呼吸リハビリを行う際は、身体の状況をよく確認する必要があります。ここでは呼吸リハビリでの注意点について解説します。
呼吸リハビリが適用ではないケースもある
呼吸器疾患の程度や症状によっては、呼吸リハビリを避けた方がいいケースもあります。呼吸リハビリを避けるべき状況は以下の通りです。
【絶対的禁忌(避ける必要がある)】
● コントロールができないショックが現れる
● 急性心筋梗塞である
● 重度の不整脈がある
● 肺血栓塞栓症である
● 肺胞の出血・喀血がある
● 未処置の気胸がある
【相対的禁忌(基本的に避けるべき)】
● 血液の循環が不安定
● 膿胸がある
● 肺挫傷や多発肋骨骨折がある
● 頸髄損傷後でも損傷部が固定されていない
● 脳外科術後に、頭蓋内の圧が亢進している
上記に当てはまる方は注意する必要があります。呼吸リハビリを行う際は、必ず事前に医師と相談をしましょう。
出典:呼吸不全における呼吸リハビリテーション - SQUARE
運動中に息が苦しくなったときの対処法
運動中に息が苦しくなったときのために、焦らずに呼吸を整える方法をおさえておきましょう。屋外で息が苦しくなった場合、近くの壁や木に寄りかかったり、膝に手を当てたりしてラクな姿勢をとります。前屈みの姿勢をとると、横隔膜が動きやすくなって呼吸がスムーズとなります。その後、口すぼめ呼吸や腹式呼吸を意識して、ゆっくりと息を整えましょう。
屋内も同じように、近くにイスがあれば座りつつ、クッションや枕にもたれてラクな姿勢をとります。息が苦しくなったときは、まずは呼吸を整えることを第一に行動しましょう。
呼吸リハビリテーションを継続するコツ
自宅で過ごしていると、運動をなかなか続けられない方もいるのではないでしょうか。ここでは呼吸リハビリを継続するためのコツについてご紹介します。
ムリのない運動内容からはじめる
まずはムリのない負荷量の運動からはじめることが大切です。いきなり負荷の高い運動を行うと身体的な負担が強くなるので、体調の悪化につながります。最初は軽い運動からはじめて、慣れてきたら少しずつ負荷量を高めていきましょう。
日によって体調は変化するので、運動中に「少しおかしい」と感じたらすぐに休憩しましょう。運動はある程度の負荷量が必要ですが、それ以上に継続することが重要です。運動習慣をつけられるように、辛くない範囲から進めていきましょう。
具体的な目標を立てておく
呼吸リハビリを行う際は、具体的な目標を立てておくと継続しやすいです。目標を立てずに運動を行うと達成感がいつまでも得られず、途中で挫折してしまうからです。「家族で旅行に出かけたい」「近所を気軽に散歩できるようになりたい」など、今後したいことを目標にすれば、運動のモチベーションも高まるでしょう。
大きな目標だけだと自分がどこまで達成しているのかわからないので、小さな目標も立てておくのもおすすめです。「1日3,000歩歩く」「毎日散歩をする」などの小さな目標を積み重ねれば、自分の成長度合いを実感できるでしょう。
呼吸リハビリテーションのポイントを理解して継続しよう
呼吸リハビリには症状やQOLの改善が期待されており、呼吸器疾患の方にとっては重要な取り組みといえるでしょう。運動だけでなく、薬の服用や栄養バランスの調整も忘れずに行うことで、呼吸リハビリの効果はさらに高まります。症状や身体状況によっては運動を避けるべき方もいるので、必ず医師に相談してから呼吸リハビリを行うことが大切です。自分のなかで目標を持ちながら、ムリのない範囲から呼吸リハビリをはじめてみましょう。関連ジャンル
最新コラム記事
-

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説
-

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説
-

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介
-

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介
-

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説
-

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説
理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説